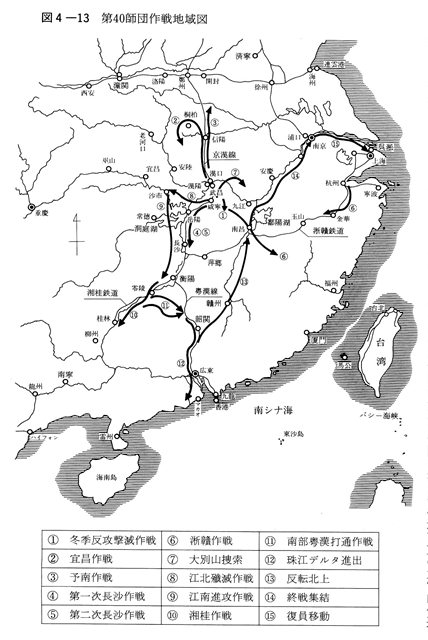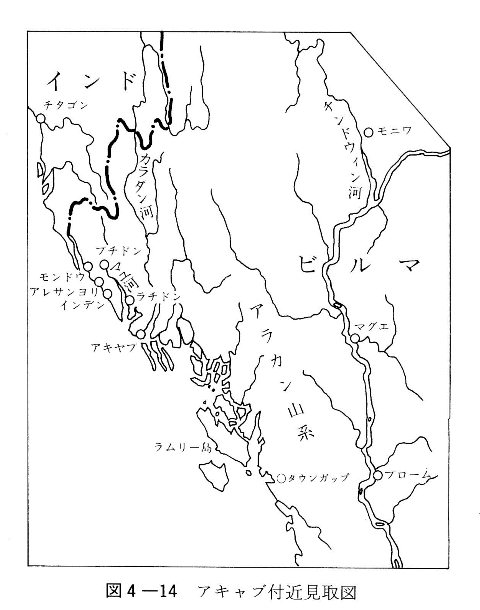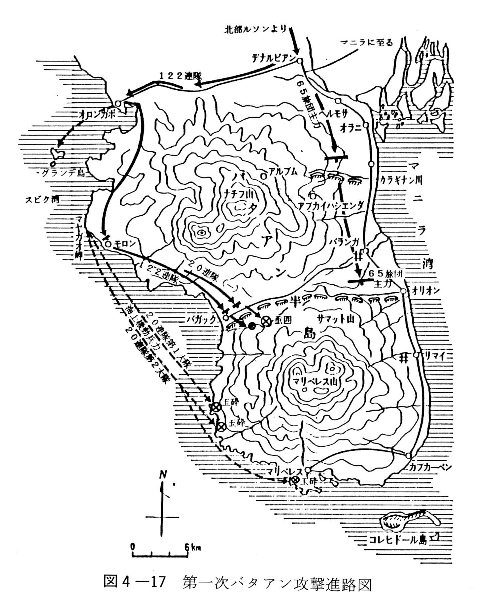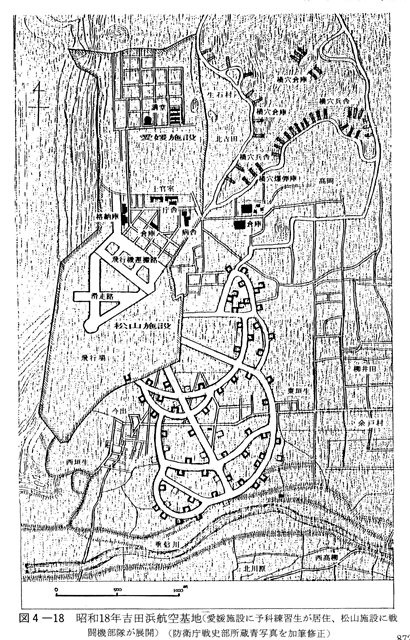データベース『えひめの記憶』
愛媛県史 近代 下(昭和63年2月29日発行)
三 その他の郷土編成部隊
独立歩兵第15大隊
昭和一三年(一九三八)二月、第二次上海事変に出征中の歩兵第22連隊補充隊において、占領地警備を主任務とする独立歩兵第15大隊(長・少佐清水喜代美)が編成された。大隊は四個中隊編成、人員八一〇名であった。22連隊が凱旋するのと入れ替わるように、四月三日出発、塘沽に上陸し、そのころ通州で編成された独立混成第4旅団(長・中将河村薫)に編入された。
旅団はその後北支における占領地の治安警備に当たり、時には国共合作により編成された八路軍(国民革命軍第八路軍の略称)に対する討伐作戦も行った。
昭和一五年八月、八路軍(三個師団、兵力四万余)は百団大戦(一〇〇個連隊による攻勢作戦の意)を呼称して、その精鋭部隊を旅団の守備する石太線(石家荘―太原間の鉄道)沿線に指向して攻撃をかけ始めた。当時大隊は本部を鉄道沿いの陽泉(石家荘西方九〇キロメートル)に置き、東西八〇キロメートルの地域を分散警備していたが、寡兵よく大軍と対戦した。守備隊は苦境に陥ったが、友軍爆撃機や同地通過中の友軍帰還部隊及び装甲列車隊の支援を得て、八路軍を奇襲攻撃することに成功した。この戦闘を契機に他の警備隊も攻勢に転じ、八月末にはその包囲網を寸断して近隣友軍との連繋を回復した。
その後も北支警備の任務は継続されたが、昭和一八年六月、第62師団(兵団符号「石」)の新設に伴い、独立混成第4旅団は歩兵第64旅団に改編され、同師団の隷下に入った。歩兵第64旅団は独立歩兵第15大隊など四個の独立歩兵大隊(大隊は歩兵四個中隊・機関銃一個中隊・歩兵砲一個中隊)を基幹に編成されていたが、この編組は後述の沖縄作戦まで持続された。
独立歩兵第15大隊は同年七月以降、山西省段村付近の警備に就き、同月には太行作戦、九月には太岳地区作戦に参加した。翌一九年四月からは河南作戦に参加し、六月以降は河南省新擲密県付近の警備を担当した。
同年七月、第62師団は大本営直属となり、青島に集結を命じられたが、転進を準備中師団は第32軍の戦闘序列に編入され、改めて集結地を上海に変更された。師団は八月一六日上海を出航し、一八日に沖縄本島那覇港に上陸した。歩兵第22連隊上陸の一〇日後のことであった。
上陸後第62師団は第9・第24師団の中間(浦添・普天間一帯)に配備され、独立歩兵第15大隊は北谷村(普天間西北海岸線)に陣地構築作業を開始した。一二月中旬、第9師団が抽出せられると、大隊は知念岬南岸島尻郡王城村に配備を変更せられたが、このとき新大隊長(少佐飯塚豊三郎)が着任した。更に翌二〇年二月には作戦計画の変更により三たび浦添村仲西・天久(那覇北郊)に移駐し、西方海上に備える水際陣地を構築した。
四月一日、米軍が上陸作戦を開始した後も、大隊は二次上陸に備えて前記水際陣地に就いたままであったが、同月二〇日になって旅団主力正面の伊祖・城間にまで進出した米軍を阻止する命令を受け、安波茶付近で地上戦闘に加入した。同じころ歩兵第22連隊第3大隊も第62師団戦線建て直しのため、第64旅団に配属されて安波茶付近でこの激戦に参加しているが、郷土出身両大隊の協力の詳細は明らかでない。
二〇日間の激闘の末、第62師団の戦力は半減していたので、これら新鋭部隊の戦闘加入も大勢を変えるに至らず、大隊も徐々に圧迫されて五月一二日には澤岻(首里北方一、〇〇〇メートル)の洞窟陣地に残存兵力を集めてたてこもるまでになった。その後も首里防衛戦線確保に懸命の努力を続けたが、一五日には軍及び師団からの厳命があり、首里北側地区に後退した。諸隊決死の抵抗も空しく首里防衛戦線は次第に破綻を来し、大隊は二五日には津嘉山(首里南方二・五キロメートル)に、次いで六月三日には島尻最南端の喜屋武地区に撤退した。一五日夕刻、大隊は師団命令により米須(喜屋武東三キロメートル)北側に進出し、摩文仁の軍司令部に殺到する戦車の一部を撃退したがついに戦力尽き果て、二〇日に至って大隊長以下玉砕した。
歩兵第62連隊
日露戦争の講和の動きが出始めた明治三八年(一九〇五)七月、歩兵第62連隊が第16師団(京都)の隷下に誕生した。第1大隊は姫路、第2・第3大隊は四国の各歩兵連隊補充隊の兵員をもって編成された。連隊は満州駐剳の草分けとして同年八月、大連に上陸し各地の警備の任に就き、四〇年三月帰還したが、この間歩兵第22連隊からも補充要員が送られていた。
帰還後、同連隊は大阪の天下茶屋に仮屯営していたが、明治四〇年一〇月の改編により、第11師団第10旅団(徳島)の隷下に入り、徳島県加茂村に移駐した。大正一四年(一九二五)の宇垣軍縮の際、連隊は廃止の運命を負い、軍旗を返納して一度は消滅した(第三章第七節参照)。
昭和一三年(一九三八)四月、第21師団(青森・兵団符号「討」)の隷下として再び歩兵第62連隊(長・大佐澤田保富)が編成された。連隊本部と歩兵砲・通信隊が丸亀、第1大隊が松山、第2大隊が徳島、第3大隊が高知において編成されたものであるが、その後の補充は師団所在地の東北地方出身者によって行われた。
同年七月、連隊は先に返納した軍旗を再び拝受し、九月四日、坂出港にて乗船し征途に就いた。
〈北支に転戦〉
九月九日、塘沽に上陸した連隊は、宿縣(徐州南方七〇キロメートル)に連隊本部を置き、津浦線・大運河・東部朧海線周辺の警備・治安粛清の任に就いた。翌一四年二月以降は蘇北作戦・于学忠討伐作戦・渦河河畔掃討作戦・濠城集東方地区の戦闘などに参加した。
同一六年五月からは中原作戦に参加、済源城占領後は黄河北岸及び南部山西の山岳地帯に行動し、随所にその根據地を覆滅して同作戦に大きく貢献した。
同作戦終了後六月中旬からは、保定付近一帯の警備を行った。一〇月下旬、連隊は青島に転進し、第二次魯南剿共作戦に参加しながら南方作戦の訓練に入った。
一二月八日、対米英開戦に伴い、第21師団は南方総軍の戦闘序列に入り、熱帯地域戦闘訓練に専念した。
〈比島バタアン半島に転進〉
同一七年(一九四二)二月、師団は南方軍総予備兵団として仏印に前進を開始した。この海上輸送中、第14軍による第一次バタアン作戦の挫折があり、62連隊(山砲兵一個大隊・工兵連隊主力共)は急きょ進路を変更して比島リンガエン湾に上陸、歩兵団長の指揮下に入って永野支隊となった。支隊は二月末、バタアン東海岸第一線に到着し、米比軍の猛砲撃下に捜索・出撃阻止・前進陣地の奪取に任じ、軍主力兵団及び軍砲兵群の展開を援護した。我が軍は鋭意空中及び地上近接偵察を行ったが、錯雑したジャングル内に隠ぺいした陣地の前縁は不明確で、砲兵群の攻撃支援射撃は第二陣地帯以降に指向しなければならない状況であった。62連隊が前進陣地の争奪戦によって入手した防御計画図によって陣地の全容が判明し、攻撃支援射撃が第一陣地帯に指向されるよう変更され、全軍の作戦に大きく貢献した。
四月三日、第二次バタアン攻撃が開始された。第4師団・第65旅団が第一陣地帯を抜いた後、六日には永野支隊も第一線に進出し、突破口を拡大しながら第二陣地帯を次々と奪取した。七日には米比軍の実質最終防御線であったサンビセンテ川の抵抗戦に達し、その東翼軸要地を戦車・砲兵・爆撃機の協同の下に奪取した。これによって守備軍は崩壊し、午後には総退却し始めた。
九日朝、ルソン軍司令官キング将軍自らが支隊正面に出頭し、バタアンに在った八万の米比軍は降伏した。この間も支隊は突進を続け、同日正午ころにはコレヒドール島を望むカプカーベンを占領した。支隊はその後マリベレス軍港に駐留し、五月下旬からビサヤ諸島(ネグロス・ボホール・サマール・レイテの四島)の戡定作戦を行い、一一月下旬までその警備に就いた。
〈北部仏印に転戦〉
昭和一七年一二月、支隊は転進して北部仏印に至り、第21師団長の指揮下に復帰した。歩兵第62連隊は一八年ころからヴィンエンの新兵舎に集結し、警備任務に就きながら各種戦闘訓練に精進した。
昭和一九年一二月には一部兵力が中国国境を越えて南支軍と連絡に成功した。これは南方戦線を陸路で結ぼうとした大陸打通作戦の一翼を担った作戦であった。
翌二〇年三月には明号作戦(仏印軍及び同武装警察隊に対する武力処理作戦)に参加し、仏軍を降伏させた。
終戦とともに軍旗を奉焼し、同二一年四月、浦賀に上陸復員した。
第40師団(鯨兵団)
昭和一三年、中支派遣軍は武漢三鎮(武昌・漢口・漢陽、現在の武漢)を占領したが、広大な大陸にあって確保したのは、主要都市とそれを結ぶ点と線とに過ぎなかった。
昭和一四年八月、これら占領地警備を主任務とした第40師団が、善通寺師管において編成された。
このころから防諜のため部隊の個有編制番号を用いず、一般に兵団符号が用いられた。第40師団は四国編成に因んで「鯨」兵団と呼ばれた。
師団は歩兵三個連隊編制という三単位師団で、歩兵第234連隊が松山、235連隊が徳島、236連隊が高知、師団及び歩兵団司令部、騎・山砲・工兵連隊などは善通寺が編成地とされた。このため234連隊(初代連隊長・大佐重松潔)は郷土部隊としての色彩が強かったが、愛媛県人で236連隊(高知)や特科連隊に入隊した者も少なくなかった。歩兵連隊には九月一三日、宮中において軍旗が授与された。師団は十分な訓練の期間が与えられぬまま征途に就くことになり、第234連隊は一〇月六日、松山の兵営を出発、翌七日坂出港を出港した。師団主力も続いて出発、揚子江をさかのぼり同月一五日から一九日にかけて武昌及びその近辺に上陸した。師団は第11軍の隷下に配され、司令部を咸寧(武昌南方七五キロメートル)に置いて梁子湖南部の広い地域の警備に就いた。
〈冬季反攻撃滅作戦〉
漢口から重慶に後退した蔣介石は、再びその揮下の部隊を整備訓練し、日本軍の占領地に大規模の冬期反攻を計画していた。一二月一〇日、その中の五個師約七万の部隊が我が警備地南方の九官山付近に進出し、第234連隊の守備地に殺到した。師団はその主力をもってこれを攻撃し、夜襲や敵前渡河を行って九官山以南に撃退した。二四日再び残存兵力が集結し反攻の気配を見せたので、騎兵連隊と歩兵三個大隊が出動しこの兵力も撃退した。
このころ隣接の第6師団は約一〇万の中国軍に包囲され、各守備隊とも分断され苦戦中であった。歩兵団長石本少将の指揮する石本支隊は陸水を越え通城(咸寧南方九〇キロメートル)北方に進出し、二個師の中国軍を撃破して第6師団を救援した。翌一五年一月、同師団は再び中国軍の重囲に陥ったので、235連隊の二個大隊はまたも通城付近に前進し、山地に陣地を占領した中国軍を撃退した後帰還した。再度にわたる救援作戦は、第6師団将兵から厚い感謝が寄せられた。
師団長(中将・天谷直次郎)は警備・作戦の他に占領地の民生安定にも意を用い、将校の中から政治・経済・農業などの専門家を集めて研究会を開き、道路の整備や農園の開発など町づくりも積極的に進めた。
〈宜昌作戦〉
昭和一五年(一九四〇)五月、第11軍は宜昌に対する進攻作戦を開始し、師団も軍の支作戦としてその北方地域に主力をあげて参加した。小林店付近に組織的な火網を構成した堅塁は、激闘の末四日に占領、桐柏を経て更に西進したが、湖陽鎮では第234連隊第3大隊(この大隊のみ丸亀編成)が中国軍の重囲に陥り、大隊長戦死、配属山砲二門を奪われるという苦戦があった。
〈予南作戦〉
昭和一六年一月、第11軍は漢口北方に集結した中国軍に対する攻撃作戦を開始した。師団もこれに参加、京漢線東側を北上し、二八日には蒙古風を冒して急進した騎兵連隊が汝南城(信陽北方一二〇キロメートル)を、二月一日には中国第85軍の本拠地であった領域を占領した。
〈第一次長沙作戦〉
同年夏、日本軍は「関特演」(関東軍特別演習の略称)を発動、七五万の兵力を北満に配備した。世界の耳目はこれに集中したが、支那派遣車においても中国戦線における日本軍の健在を誇示するため、要衝の長沙を攻撃する計画をたてた。師団の任務は第11軍主力師団の左側背を援護することであったが、九月一一日、粤漢線沿いに南下を始めて間もなく、沙港河付近で予期せぬ中国軍大部隊と遭遇した。連日激しい攻防が繰り返されたが、一八日、軍は一斉攻撃を行い、師団は更に南下した。二四日、長沙最後の防衛線甕江の陣地に達し、激戦の末これを占領、二七日には長沙東五〇キロメートルに進出した。同日軍主力は長沙を占領し、本作戦の目的を達した。師団は三〇日から反転を開始し、一〇月中旬原駐屯地に帰還した。一二月七日、234連隊では転勤した重松連隊長の後任に大佐・戸田義直が着任した。
〈第二次長沙作戦〉
同年一二月、太平洋戦争開始とともに、南支軍は香港を攻略することになった。この作戦の背後にある中国軍を牽制するため、第11軍は再び汨水(長沙北方七〇キロメートル)に進出する約二週間の作戦を計画した。一二月二四日、師団は行動を開始し、夜襲を繰り返して二七日には汨水の線まで進出した。このころ寒気が一段と加わり、道路は寸断されて泥まみれの前進は難渋し、また中国軍の抵抗はかつてない頑強なものであった。二九日、増水した汨水の敵前架橋に成功し、その南岸に進んだ第一線部隊は磨刀尖一帯の高地に拠る中国軍を猛攻し、激戦の後これを撃退した。香港は南支軍が二五日占領したので今次作戦の目的は達成されたが、軍司令官は急に予定計画を変更し、独断長沙への進攻を決意した。師団は軍主力師団の左翼援護のため、更に南下し金井(長沙北東四〇キロメートル)へ突進するよう命じられた。二週間の応急出動の携帯弾薬・糧秣は其の後の補充もないまま、大晦日・元旦と夜を徹して行軍を続けたが、中国軍の戦術により現地の食糧品はすべて撤去されていた。昭和一七年一月二日、師団は我が軍主力の左側背に迫る中国軍大部隊と遭遇した。金井付近の要地を確保し軍主力を援護すべく迎撃態勢をとったが、人海戦術の大軍に包囲され苦戦を強いられた。更に三日夜、軍から「第40師団は一部を金井付近に残して軍の側背を援護させ、主力は即時春華山に前進して軍主力の反転を援助せよ」との緊急命令があった。金井残置部隊となった第236連隊は大山塘付近高地に陣地を構築し、弾薬と食糧の欠乏に耐え、多くの犠牲を払いながら銃剣と気力のみでこの地を死守した。この間師団主力は春華山(長沙東方二〇キロメートル)に進出、中国軍の重囲に陥っていた軍主力の反転行動を援護した後、七日夕、自らも反転し先の残置部隊を救出収容した。その後も退路遮断を企てる優勢な中国軍の追尾を受けながら悲惨な行軍を続け、一五日に原駐屯地に帰還した。
〈浙贛作戦〉
昭和一七年四月、米軍中佐・ドウリットルの指揮するB25爆撃機は東京を初空襲し、中国大陸の浙江省の飛行場に着陸した。支那派遣軍は急きょこれら浙贛鉄道沿いの飛行場群を覆滅する作戦を計画した。師団からは河野混成旅団(歩兵団長・河野少将の指揮する歩兵三個大隊・山砲一個大隊・工兵一個中隊)と今井支隊(第236連隊長・今井大佐の指揮する歩兵四個大隊・山砲一個大隊・工兵一個小隊)が編成され、この作戦に参加した。
河野混成旅団は輸送されて杭州に上陸し、上海の第13軍の隷下に配属され、同地から浙贛鉄道南側を西へ進撃した。六月三日払暁から軍の総攻撃が始まったが、混成旅団はその中央にあって樟樹潭の堅陣を抜き、烏渓江を敵前強行渡河して、七日には衢州城を占領した。一二日には江山(杭州より西方二〇〇キロメートル)に達し、八月一九日まで同地付近の警備に任じた。この間軍主力は金華・衢州・常山などの飛行場を潰滅させ、戦略物資の後送も終了して作戦目的を達成したので、旅団は第13軍の隷下を脱し、南京を経て原駐屯地に帰還した。
今井支隊は南昌を出発し、浙贛鉄道を東へ進撃する第34師団の作戦を容易にするため、同地東南方に作戦した。六月六日には展坪墟において中国軍大部隊の側面を不意急襲して大きな戦果をあげた。支隊はその後豪雨で河川がはん濫したため難渋の行軍を続け、宜黄・建昌(南昌東南一四〇キロメートル)に進出し目的を達成した。
〈大別山捜索〉
昭和一七年一二月中旬、第11軍司令官・塚田中将とその幕僚の搭乗機が大別山山系で遭難した。軍は直ちに捜索のための作戦を起こし、師団からは第234連隊を基幹とする戸田支隊が派遣され捜索に従事した。支隊は一二月二〇日から翌一八年一月五日の間、揚子江北岸の英山付近に行動して捜索に当たった。
〈江北殲滅作戦〉
師団の警備地の揚子江を隔てた西対岸の沔陽地区には、王勁哉の率いる三万余の軍勢が堅固な堡塁を構築していた。我が軍はこの地域が武漢地区への物資の供給源でもあり、これを温存し懐柔工作を続ける政策をとっていた。王もまた日本軍と適当に接触を保ち、巧みに交戦を避けていたが、我が軍は一七年末になってこの工作に見切りをつけ、武力攻略を決意しなければならなくなった。師団は堡塁攻撃訓練を重ねた後、一八年二月一三日、岳州北方で揚子江を渡河し、周到に築城された堡塁を次々と攻略して二〇日には新廠(岳州西北八〇キロメートル)を占領した。師団主力は休む間もなく反転して洪湖北岸に急進し、別行動で赤壁山付近を渡河した仁科支隊(第235連隊基幹)と東西から王軍主力を挾撃した。師団は更に揚子江南岸の華容地区に進出して掃蕩作戦を行い、第234連隊をこの地区の警備に当たらせ、主力は原駐屯地に帰還した。
〈江南進攻作戦〉
このころ、我が国の船舶は不足を訴え、軍事輸送力の低下の兆しが見え始めていた。軍は揚子江上流の宜昌付近に繋留されたままの約二万トン(五〇隻余)の船舶を下航させる必要に迫られ、一時的に江南地区に進攻してその航路を安全に確保する作戦を開始した。その第一期作戦に南縣一帯の中国軍を撃滅すべき任務を与えられた師団は、戸田・小柴両支隊を編成し、五月五日それぞれ華容・石首付近から南下を開始した。両支隊は渡河作戦や水郷地帯作戦の辛苦をなめながら、一〇日には洞庭湖北岸の三仙湖市に進出し目的を達成した。この間小柴支隊に配属された234連隊第3大隊は、七~八日の荷花市攻撃において、中隊長三人を含む四〇余人の戦死、六〇数人の戦傷者という甚大な損害を出した。両支隊は六月上旬まで占領地の警備に任じ、軍の作戦目的達成とともに反転を開始して原駐屯地に集結した。このとき第13師団は中国軍の積極的反攻に遭い、離脱困難となったので、小柴支隊と234連隊第1大隊は再び出動し、これを援護する戦闘に従事した。
〈編制の縮小〉
昭和一八年(一九四三)七月、軍令によって編制の改正が行われた。師団は歩兵団司令部がなくなり、山砲兵連隊は第31師団(兵団符号「烈」)に、第2野戦病院は第15師団(兵団符号「祭」)にそれぞれ編入され、いずれもビルマに派遣された。この両部隊はその後インパール作戦に参加し、悲惨な運命をたどることになる(「山砲兵第31連隊」の項参照)。また数々の武勲に輝いた騎兵隊も各歩兵連隊に乗馬一個小隊ずつを残して解消し、工兵連隊は二個中隊、輜重兵連隊は一個中隊に縮小され工兵隊・輜重隊と改称されることになった。
これと同時に師団司令部は咸寧から岳州に移り、警備地も234連隊が石首・華容地区、235連隊が桃林地区、236連隊が長安地区と移駐した。
〈常徳作戦〉
同年一一月、軍は重慶への要衝常徳攻略の作戦を開始した。234連隊主力は第68師団の指揮下に入り、水郷や湖の舟艇機動を繰り返して常徳に迫り、二九日には東門から常徳城に突入し掃討を行った。その後も転戦して多大の戦果をあげ、一二月二一日、原駐屯地に帰還した。
〈湘桂作戦〉
昭和一八年秋、中国南東部の江西省を基地にした米空軍が突如台湾に来襲した。これは日本本土への空襲の前触れであり、更にB29重爆撃機が配備されたときには中国南西部からの空襲も可能であることが考えられた。昭和一九年五月、第11軍は武漢地区から作戦を発起し、南西部主要基地である衡陽・桂林を攻略する作戦計画を立てた。師団は舟艇機動や水郷地帯の戦闘に長じていたため、軍の最右翼兵団として洞庭湖を渡って南下する進路が与えられた。今回の作戦は桂林まで六五〇キロメートルに及ぶ長大なものであり、再び原駐屯地に帰還する予定はなかった。この作戦計画は補給の目途のないまま立てられたもので、第一線諸隊は現地における徴発によって糧を求めなければならない条件を背負わされていた。またこのころ彼我の航空勢力は逆転し、絶えず米軍機の攻撃にさらされる状況に陥っていた。師団は先の江南進攻作戦の経路を再び南下し、六月一日、幸いにも降雨のため米軍機の妨害を受けることなく、洞庭湖を奇襲渡湖し南岸に達したが、一一日、湖畔にあって患者後送を準備中の野戦病院は米軍機六機の爆撃と機銃掃射を受け、死傷者が続出した。師団は益陽を攻略して南下を続け、三〇日には衡陽北西地区に進出したが、この時軍の主力師団は衡陽の包囲攻撃を開始していた。七月に入って衡陽攻城中の我が軍主力を逆包囲する目的で、二個軍八万の中国軍が桂林方面から迫って来た。師団は衡陽西方一〇キロメートルの山地に展開し、攻城中の軍主力と背を接して押し寄せる大軍を迎えた。中国軍は米軍機の支援を受け、優勢な砲兵の火力を集中して本格的な攻撃を加えて来た。各連隊とも圧倒的多勢の中国軍を相手に善戦したが、次第に弾薬・手榴弾が不足し、第一線陣地では侵入した中国兵と各所で白兵格闘が演じられるまでになった。この状況下にあって、234連隊では軍旗を一時攻城中の第58師団司令部の位置まで後退させ、連隊長以下残存兵力が全滅を期して陣前に出撃するなど悪戦苦闘が続けられた。この間攻城部隊は八月七日衡陽を陥落させ、逆包囲を企図した師団前面の大軍も攻撃を中止した。
八月末、軍は桂林攻撃のためまず全縣(現在の全州)地区へ進出集結を開始した。師団も湖南・広西両省境の重畳した山岳地帯を踏破し、九月一五日には目的地に集結した。
一〇月二〇日、桂林攻略が下命されたが、第40師団は今までの軍主力の側背援護任務と異なり、第一線兵団として起用されたので志気は高揚した。師団は桂江東岸地区を前進し、三一日には桂林の東側を流れる桂江東岸の要地七星巌に達した。この一帯の岩山は地形峻険に加え洞窟が多くて砲爆撃もほとんどその効果がなく、更に鉄条網・地雷が設けられ、桂林南方砲座からの側防砲火も準備された天然の要塞であった。一一月四日から開始された攻撃は凄惨を極めたが、七日夕になってついにこれら高地を占領した。九日〇〇〇〇、第236連隊の二個中隊が折畳舟によって強行渡河を敢行したが、工兵隊とその舟艇は多大の損害を被り、第二次以降の渡河は完全に阻まれてしまった。これを見ながら東岸の主力部隊は河越えの支援射撃でこれを激励するのみであった。渡河部隊は多大の損害を受けながらも砲兵陣地を制圧したので、渡河点に対する妨害射撃は著しく減殺された。夜に入って再び渡河が開始され、一〇日天明とともに一斉に桂林市街に突入した。
〈南部粤漢打通作戦〉
フィリッピン戦況の悪化に伴い、南支那海々岸にも米軍の上陸が懸念される事態となって来た。師団は新たに満州から転用された第20軍の指揮下に入り、南部粤漢線の鉄道施設を挺進奇襲により無傷占領すべき命令が与えられた。師団はそれぞれ大隊長を指揮官とし、体力強健・剛健の隊員を選抜して、甲・乙・丙・丁四組の挺進隊を編成した。便衣に変装し、携帯兵器や通信機材はカゴに収めて担った挺進隊は、同二〇年一月三日から一〇日にかけて次々と潜行を開始した。各挺進隊とも百数十キロメートルの山路を踏破し、一月一八日から二一日にかけ、広東省々境一帯の粤漢線に達し、二~三箇所の爆破以外ほとんど無傷で新岩下鉄橋を含む鉄道施設を占領した。後続した師団主力も二三日には到着し、輝かしい成果をあげて打通作戦は完了した。
その後師団は234連隊を粤漢線警備に残して南下を続け、二七日には南から攻撃中の第104師団と挾撃して韶関を占領、また一部は東進して二月七日、南雄飛行場を占拠した。当面の作戦を終了した師団は主力を韶関付近に集結し、一部を南雄・始興に分駐して警備に任じた。
師団は三月一日、第23軍の指揮下に入るとともに、粤漢鉄道警備のため急きょ編成中の第131師団のために、独立歩兵598大隊と同594大隊の二個大隊を分割編成して差し出した。
三月中旬、師団は234連隊を鉄道沿線警備に残し、主力は広東を経て江門に進出、珠江デルタ地区に展開し、米軍上陸迎撃に備え、水際陣地を構築し訓練を開始した。しかし四月一日、米軍の沖縄上陸によって南支への上陸の可能性は無くなった。四たび配属が変更され、今度は支那派遣軍の予備隊を命ぜられ、南昌に向け行軍することになった。
〈反転北上〉
六月一日、師団は広東を出発、途中妨害する中国軍を撃退しながら七月上旬に贛縣(現在の贛州)に進出、ここで234連隊と合流し、更に果てしない行軍を続けた。八〇〇キロメートルに及ぶ長行軍に疲れきった師団が鄱陽湖畔に達した八月一五日、日本の降伏が伝えられた。翌一六日夕、師団長は各部隊に終戦の詔勅を伝達し、軍旗及び書類の焼却を命じた。一九日から再び行軍が開始され、揚子江岸の九江・蕪湖・馬鞍山を経て一一月下旬、漸く南京郊外に到着集結した。
〈南京市内大溝の清掃〉
復員を待つ師団は、一部兵力で市内の道路及び通信線修復作業を実施した。その後更に中国軍から市内大溝を清掃する依頼が持ち込まれた。溝の泥は何千年も積もった代物で、その清掃は最も卑しい作業とされていた。しかしこの依頼が懲罰・復讐の意味でなく、永年中国人が為し得なかったことを日本軍に頼むという真意が判明し、師団長はこれを快諾した。宮川師団長は部下将兵にこの作業の意義を諭した。計画割り当てに従って清掃作業が始められたが、予定された期間の半ばでこれを完了し、更に掘り割りまで増設し、中国の官民から多大の感謝が寄せられた。
翌二一年二月から再び道路の修理作業に任じ、五月に入って上海地区に移動、中旬から米軍上陸用舟艇に分乗し故国に復員した。
第55師団(楯のちに壮兵団)
昭和一五年(一九四〇)、欧州戦線ではフランスが降伏し、太平洋地域においても米・英との緊迫度が次第に高まっていた。第40師団が編成された一年後の同年八月に、第55師団が再び善通寺師団管内において編成された。
防諜のための兵団符号は、防人の歌からとった「楯」が用いられたが、三代目花谷師団長が着任して「壮」と改められた。
師団は歩兵三個連隊編成で、歩兵第112連隊が丸亀、143連隊が徳島、144連隊が高知、司令部及び騎・山砲・工・輜重兵連隊などは善通寺の各連隊留守隊で編成された。松山での編成は行われなかったが、県人は特科部隊特に山砲兵連隊に入隊した者が多かった。歩兵連隊には九月二七日、軍旗が授与され、それより約一年間上陸作戦の戦技を中心に訓練を重ねた。
昭和一六年九月二六日、動員令が下り、応召者が兵営に参集したが、時局柄秘密裡に実行されたので近郷の盛大な歓送などは行われなかった。師団は一一月六日、第15軍の隷下に編入され、タイ国に進駐して第25軍(マレー作戦実施軍)の側背を援護し、その後はビルマ作戦の準備を行うことになった。
このとき第55歩兵団長の指揮する歩兵第144連隊基幹の南海支隊は大本営直轄として抽出され、グアム島攻略にあたった(「南海支隊」の項参照)。
師団(長・中将竹内寛)は一一月中旬、坂出・託間両港を出港し征途に就いたが、この時も見送りの人影はなかった。師団主力は同月下旬、当時仏領印度支那の海防に上陸、一二月八日、太平洋戦争開始と同時に西貢を経てタイ国に進駐を開始した。また歩兵第143連隊基幹の宇野支隊は、マレー半島に敵前上陸した第5師団に続いて、その北部のタイ国領に上陸し、所命の飛行場を占領した。その後同支隊はクラ地峡を越えて前進し、一四日にはアンダマン海側ビルマ領最南端の要衝ビクトリアポイント(現コータウン)を占領した。支隊はその後も北上を続け、一二月二七日、首都バンコクに到着、仏印方面から進出して来た師団主力に合流してその指揮下に復した。
〈ビルマ進攻作戦〉
マレー作戦は順調に進展し、日・タイ協同作戦協定も成立したので、第15軍はビルマに駐屯する英・印・中連合軍に対する進攻作戦を開始した。一二月下旬、行動を開始した師団は、タイ・ビルマ国境の山岳密林地帯を縫うように前進し、山蛭・さそりに悩まされながら、翌一七年一月下旬になってビルマ領内に進出した。三一日にはモールメンを占領し、二月二〇日にはモールメン対岸マルタバンに拠る英印軍を撃破し、三月三日、シッタン河を渡河してペグーに迫った。ペグー守備英印軍は七日朝、ペグー河に架かる橋梁を爆破して退却したので、同目夕刻には市街の掃討を終え、ラングーン防衛の要地は我が軍手中に帰した。
三月一四日、師団はトングーに向け北上進撃を開始した。二〇日、前衛は戦車を有する部隊と遭遇したが、これはビルマ戦線で始めて出遭った中国重慶軍であった。師団は二六日から堅固な陣地が構築されたトングーの攻撃を開始し、三〇日朝には工兵隊が陣地核心部の爆破に成功し、この堅塁を抜いた。
四月はこの地方の最も暑い時季で、日中は四〇度を超える焦熱地獄となったが、師団は中国軍の抵抗を撃破しながら北上を続け、四月一九日にはピンマナに進入した。その後も第18師団とともに突進を続け、二六日にカンダンの英印軍を撃破し、五月四日に中部ビルマの要衝マンダレーに入城した。その後もマンダレー北方地域の掃討を行うとともに、六月には一部兵力をミートキーナ(現ミッチーナ)を越えて遠く緬支(ビルマ・中国)国境に派遣し討伐に当たらせた。この後約半年間、師団はマンダレー周辺地区に分散駐屯して警備に任じた。
〈第一次アキャブ作戦〉
昭和一八年一月、師団は印度洋に面する西南部ビルマのアキャブ地区への転進を命じられた。この地域は日・英両軍とも攻勢に転じるのに必要な戦略上の要点であった。一度はビルマ国外に駆逐された英印軍も徐々に態勢を建て直し、一七年末ころから反攻に転じ始めていた。この地には第33師団の歩兵二個大隊を基幹とする宮脇支隊が守備に就いていたが、優勢な英印軍に徐々に圧迫され、後退を余儀なくされていた。
師団は長駆南下を開始したが、アラカン山系が大部隊の機動を許さないので、プロームを経てタウンガップに進出、同地からアキャブまでは舟艇機動によった。しかし舟艇の不足と英軍機の跳梁によりその輸送は思うようにはかどらなかった。このころ新たに任命された師団長(中将古閑健)は、内地からビルマに着任すると直ちにアキャブに飛び、死闘を続けていた宮脇支隊を掌握するとともに、二月初旬には112連隊長とその軍旗及び騎兵連隊長を飛行機によりアキャブに招致した。軍旗の第一線進出により守備部隊の士気は大いに高まり、一度は放棄することも考慮されたラチドン―ドンベイク(アキャブ北方四〇キロメートル)の防禦線を死守し続けた。師団長は海路アキャブに到着する隷下諸隊を直ちに戦線に投入し、辛うじて英印軍の猛襲を撃退することができた。
このころ第33師団の一個大隊は、標高三、〇〇〇メートル、人跡未踏のアラカン山系の密林を四〇日がかりで踏破し、英印軍の背後カラダン河谷に進出した。このため英印軍はにわかに動揺の色を示し始めた。
師団長はこの戦機を看破し、部下諸隊の集結を待つことなく攻勢に転じる決心をした。歩兵第143連隊はマユ半島ドンベイク陣地前に英印軍主力を拘束し、第112連隊はマユ河両岸地区から奇襲的に攻撃前進し、インデン付近でその退路を遮断してこれを捕捉撃滅する策がたてられた。二月二五日、作戦行動が開始され、112連隊は山中をひそかに北進して三月二四日からマユ河を渡河した。四月三日、師団の両連隊は呼応してインデン付近の英第6旅団(英人だけで編成された精鋭旅団)を捕捉し、旅団長を捕虜とするとともにその主力をせん滅した。さらに五月上旬にはブチドン・モンドウを奪回した。
第一次アキャブ作戦は、昭和一八年における南方戦線唯一の、しかも最後の勝利となった。
〈第二次アキャブ作戦〉
第一次アキャブ作戦終了後、ビルマ地方は雨期を迎えた。師団は第112連隊をマユ半島の海岸地域に、第143連隊をブチドン―モンドウの線に配置し、防衛態勢に入った。この時三代目師団長(中将花谷正)が着任した。
昭和一八年(一九四三)一二月、さきに大本営直轄として抽出転用されていた第55歩兵団(長・少将桜井徳太郎、歩兵第144連隊基幹)がその任務を終えて師団に復帰し、師団は初めて完全な編制に戻った(「南海支隊」の項参照)。
昭和一九年一月、南方軍は大本営の危惧を強く押し切って、インドに進攻するインパール作戦に踏み切った。このためインパール攻撃は第15軍に専念させ、新たにアラカン方面の作戦を担当する第28軍(司令官・中将桜井省三)が設けられた。その隷下には第54・第2師団も含まれていたが、あるいは戦場到着が遅れ、あるいはその一部が他方面に転用されて、アキャブ正面の戦線に増援することにならなかった。
第15軍はインパールに対する進攻開始時機を三月中旬と決定した。師団にはその支作戦として、アラカン地域の英印軍を極力吸引し、第15軍の主作戦に貢献すべき任務が与えられた。当時印緬国境近くインド領のチッタゴン付近には英印軍三個師団が集結し、徐々に南下の気配を見せ、第一線の143連隊はその圧力を受けていた。特にマユ山系中央部を防衛する同連隊第1大隊は坑道陣地に拠って数倍の攻撃軍を支えて健闘していた。
同大隊が苦戦の間、師団は許す限りの兵力を集結し、ひそかに攻勢移転の準備をしていた。歩兵団長の指揮する桜井兵団(歩兵五個大隊・砲兵一個大隊・工兵連隊主力)が編成され、二月三日夜半から行動を起こして英印軍背後を急襲する作戦が開始された。兵団の諸隊は極力企図を秘匿してカラバンジン河東岸を北上し、五日には英印軍補給基地のトングバザーを奇襲占領、直ちに左に旋回して印度第7師団の司令部を急襲し、激闘の末これを潰滅させた。この好機に乗じてブチドン・モンドウの守備隊も攻勢に転じ、次第に印度第5・第7両師団を追い詰め包囲し、その退路をも遮断した。
包囲された英印軍は、昼間は地形の死角を利用して分散し、夜は戦車を円形に配置してその間隙には鉄条網・自動火器・火焔放射器を並べて夜襲に備えた。これは窮余の一策ではあったが、我が軍が有力な砲兵を伴わないこと、制空権を失いつつあることを見越してのことであった。一三日にはインパール作戦から割かれた友軍爆撃機が爆撃を行ったが、弾薬約二、〇〇〇発を爆破したにとどまった。英印軍は航空兵力を集中し、円筒型陣地に対し弾薬はもとより、日用品まで迅速に空中補給を敢行した。その補給は七〇〇回を超え、総量は二、三〇〇トンに及んだ。
桜井兵団長はこの円筒型陣地に対し浸透的な夜襲を反復した。しかし円筒型陣地からは昼間のように照明弾が打ち揚げられ、戦車の火砲と自動火器は近接する将兵をなぎ倒した。被包囲軍は潤沢な補給を受け、包囲軍は弾薬・食糧にも窮するという戦史にも前例のない苦境に陥った。更に英軍側新鋭三個師団が南下し、我が背後を脅かす態勢をとり始めた。作戦発起以来二〇日間、極度に戦力の低下した兵団は、二月二六日に至り遂にシンゼイワ盆地の包囲を解き、作戦発起前の陣地に撤退した。
この戦闘はインパール作戦に呼応し、英印軍を吸引牽制する目的は達成したが、師団の受けた打撃は甚大であった。英印軍は後退する我が軍に追尾して前進し、新たな兵団を第一線に増加して猛攻を開始した。師団諸隊は反撃につぐ反撃をもって抵抗したが、優勢な戦車群に圧倒されて三月一〇日にはブチドンを奪われ、続いてマユ半島中央山系の陣地の一角にもその浸透を許した。このころには各守備陣地の兵員数は極度に減少し、補給も皆無で兵員の体力は無惨に衰えていたが、それでもなお闘志を失うことなく、寸土を争う戦闘が続けられた。
第15軍のインパール作戦の進行に伴い、英印軍の兵力特に機甲部隊の該戦場への転用が始まった。このため師団正面に対する攻撃は徐々に弱化したので、師団は再びブチドン―モンドウの線を回復整理した。五月に入ると砲声も次第におさまり、ビルマは再び雨期を迎えた。
〈シッタン河東岸へ転進〉
第15軍のインパール作戦は、雨期に入っても強行されたが、またもその陣地を攻めあぐね、七月一〇日にはその中止が伝達された。方面軍は敗退するこれら各師団を収拾して南部ビルマを確保する策を立てた。このため55師団も二年間にわたり死闘を繰り返したアラカン地区を捨て、イラワジデルタ地帯へ転進するよう命じられた。師団は八月中旬から行動を開始し、泥濘の山路を踏破、または海岸沿いを舟艇により後退し、九月中旬には同デルタ地帯の配備に就いた。この主力の後退に際して歩兵団長の指揮する桜支隊(兵力一、五〇〇)は三〇倍に余る英印軍に対し、果敢な挺進遊撃戦を反復し、雨期明けまでブチドン東西の線から英印軍の進出を許さず、その援護の任務を果たした。その後は自らも反転し、昭和二〇年一月にはプロームに集結した。
同年二月に入ると、イラワジ河を渡河した連合軍は穿貫的に要衝メークテーラに突入し、同飛行場はその手に落ちた。三月中旬にはマンダレーも失い、有力な機甲部隊はその南方にまで進出して来た。転進後退中のビルマ方面軍の各師団は随所に分断包囲され、上級司令部との連絡も途絶して収拾し難い破綻に陥っていた。またアラカン山系東側のエナンジョン油田地帯にあった独立混成第72旅団もアラカン山系から進出した機甲部隊に圧迫され苦戦となっていた。このため55師団はイラワジデルタ地帯の警備を止め、分割されてこれら友軍諸兵団の危急を救う任務が課せられた。
歩兵第112連隊(この作戦の時于城兵団と称した)は独立混成第72旅団に増援を命じられ、エナンジョン油田東北のポパ山付近に前進し陣地を構築した。連隊は五〇日にわたり該地を固守し、マンダレー街道を撤退する方面軍主力の側面を援護する重責を果たした。
騎兵第55連隊(歩兵一個大隊配属、神威部隊と称した)は、プローム付近一帯の対空挺警備に就いた。その後エナンジョン方面から浸出した機甲部隊がプロームに前進するのを阻止した後、五月中旬以降ペグー山系に集結した。
新歩兵団長(少将長沢貫一)指揮下の部隊(歩兵第143連隊主力・山砲兵第55連隊主力基幹、振武兵団と称した)はイラワジデルタの防衛に就く予定を変更し、ペグー山系に集結するよう命じられた。
師団長は残余の部隊(歩兵第144連隊主力・工兵第55連隊主力・山砲一個大隊基幹、忠兵団と呼んだ)を率い、第33軍司令官の指揮下に入り、その撤退を援護する任務が与えられた。144連隊の一部は四月一五日、ピンマナ北方シンデ河橋梁に達し、この地点で進攻機甲部隊を阻止して第33軍の撤退を援護した。忠兵団主力もこれに続いてピンマナ西方高地に陣地を占領したが、一九日には南下する優勢な機甲部隊に突破された。やむなくシッタン河左岸トングー東方地区に転進し、進攻する英印軍を拒止しながら追及する隷下諸隊の掌握に努めた。
六月に入って兵団はモールメンに撤退を命じられ、雨期のモーチ街道三〇〇キロメートルを死の行軍で踏破し、七月上旬、同地に撤退集結した。
これより先、マンダレー街道をばく進する英印軍機甲集団は五月四日ラングーンに突入していた。方面軍司令部は逸早くモールメンに後退したが、指揮連絡は混乱の極に達した。
忠兵団以外の55師団大部分の兵力は、第28軍司令官の指揮下でペグー山系中に孤立し、エナンジョン、アラカン両方面からする英印軍に挾撃される形となっていた。山中にさまよう将兵は筍・野草に蛇・とかげなどを捕食して露命をつないでいた。軍司令官は全力をあげて各部隊の掌握に努め、六月下旬になって、シッタン河を渡河してその東岸に集結することを命令した。しかし打ち続く戦闘に疲労しきった兵士の多くはマラリア・赤痢などに冒され、傷病者を担送する余力もなかった。このため手榴弾で自決する者も相次ぎ、悲惨な場面が出現した。この撤退作戦は七月二〇日ころから開始され、先ず夜陰にまぎれて英軍支配下のマンダレー街道をひそかに横断、次に一面の湖と化した畑地を胸までつかりながらシッタン河に達した。携えた竹で筏を組み、手漕ぎで渡河を開始したが、雨期のため増水した濁流に多数の負傷者や病弱者が水没する悲劇がここでも起こった。
しかし八月五日ころには大部分の兵力は渡河に成功し、次々にシャン山系西麓に集結した。
シャン山系西麓に集結した諸隊に終戦の報せが届いたのは、八月一五日から一週間以上も経ってのことであった。歩兵連隊は軍旗を奉焼し、それぞれ集結して武装解除を受け、収容所に集められて連合軍の労役に服した。
先にモールメンに集結した忠兵団は、更に鉄道輸送により七月二九日、プノンペンに到着、八月一五日の終戦を迎え、進駐した英軍次いで仏軍の武装解除を受け、西貢地区に移動して労役に服した。
ビルマ作戦に参加した第55師団の総人員は二万〇、二五九名、戦没者は一万六、三一一名、故国に生還した者はわずか三、九四八名であった。
南海支隊
昭和一五年(一九四〇)八月、第55師団が編成され、翌一六年九月、動員が下令されたが、このとき師団の一部が分割され、南海支隊が編成されて大本営直轄となった。兵力は歩兵団長(少将堀井富太郎)の指揮する歩兵第144連隊・山砲兵第55連隊第1大隊及び騎兵・工兵・輜重兵各一個中隊で、衛生隊・野戦病院・防疫給水部などの一部が配属され、独立して一方面の作戦を担当する態勢をとっていた。
〈グアム島攻略〉
支隊は海軍南洋部隊(第4艦隊基幹)と協同し、グアム島を攻略する任務が与えられた。グアム島はマリアナ諸島最南端の島で、米海軍の航空基地があり海兵隊約三〇〇と若干の島民兵が守備に就いていた。
南海支隊は一一月下旬、輸送船九隻に分乗して隠密裡に坂出港を出港し、同月二八日、小笠原諸島母島の沖合錨地に集合した。支隊は一二月四日、同地を抜錨、海軍艦艇護衛の下にマリアナ諸島東方航路を経てグアム島に向った。支隊長は軍艦津軽の艦橋にあって指揮したが、途中米艦の妨害を受けることなく、八日ロタ島に到着、計画に従って各船はそれぞれ泊地(上陸作戦に移るとき母船の停泊する位置)に分進した。一二月八日の開戦とともに、海軍航空隊は同島に空襲を行い、主要軍事施設を破壊した。支隊は一〇日〇二三〇、一斉に敵前上陸を開始し三方向から同島に上陸した。午前中には島内要地をすべて占領し、夕刻にはアガニア市にあるグアム政庁に日章旗が翻った。総督マック・ミラン海軍大佐以下三〇〇余名の米海軍守備隊は降伏し、内南洋唯一の米軍基地は覆滅した。これら米海軍の俘虜はその後善通寺の俘虜収容所に送られた。
〈ラバウル攻略〉
翌一七年一月、支隊は再び海軍と協同して速やかにニューブリテン島のラバウルを攻略すべき命令を受けた。ラバウルは二つの飛行場と良好な港を有し、濠州防衛の第一線として有力な基地であった。当時約五〇〇の濠州陸軍部隊がこれを守備し、近く更に一、五〇〇の兵力が増派される情報もあった。支隊長はトラック島に赴き、第4艦隊司令長官及び直接護衛艦隊指揮官との間にラバウル攻略作戦に関し協定を行った。同月四日以降、第4艦隊は同地に対する航空攻撃を開始し、先にハワイ作戦に任じた第1航空艦隊もこれに参加し、制空権を手中にした。
支隊の乗船した船団は一月一四日、グアム島を出港し、一九日赤道を通過、二二日夜になって泊地に進入した。夜半になって支隊は主力をもってラバウル東方海岸に、一部をもって同南方海岸に上陸を開始し、ほとんど交戦することなく、二三日午前中にはラバウル市及び東飛行場を占領した。西飛行場に向った一部は密林内において守備兵と遭遇し、これを撃退して午後同飛行場を占領した。支隊はその後も島内の掃討を続け、一月末から二月初めにはページ総督以下一、〇〇〇名が投降した。
その後支隊は同島の警備に就いたが、マラリア予防対策が徹底せず、大量のマラリア患者が発生して犠牲者を出すまでに至った。
〈ポートモレスビー攻略作戦〉
ラバウル占領後、海陸軍は協力してニューギニヤ東南岸のポートモレスビーの攻略を計画した。同地には濠軍の空海軍基地があり、濠北における第一の戦略的要衝であった。この手始めとして三月六日、144連隊第2大隊は海軍陸戦隊と協同し、東部ニューギニヤ北岸のサラモアに上陸し付近を掃討した。一〇日には連合軍機動部隊及び基地部隊による航空攻撃を受けたが、サラモア付近の確保の見通しがついたので守備を海軍に委譲し、一五日にはラバウルの支隊主力に復帰した。
海軍航空部隊は反覆モレスビーを爆撃したが、その基地能力は逆に増強され、四月末には米濠軍第一線機は六〇〇機に増強された。大本営はモレスビー攻略を指示し、第4艦隊に第5航空戦隊(空母瑞鶴・翔鶴)を一時増援することにした。
南海支隊は海路モレスビーに進攻上陸する命令を受け、五月四日、第6水雷戦隊護衛の下にラバウルを出航した。ラバウルに展開していた海軍航空戦隊は全力をもってこれを支援し、広く珊瑚海からソロモン群島一帯を哨戒飛行した。しかし支隊の出港当日、ツラギに上陸した海軍陸戦隊に対して米艦載機延べ八〇機の来襲があり、米機動部隊の進出接近が明らかとなった。
六日、両軍は互いに索敵に全力を傾注したが、支隊の一四隻からなる輸送船団上にも艦載機の飛来があり、企図は暴露した。七日早朝から両軍機動部隊は激烈な海空戦(珊瑚海海戦)を展開した。このため輸送船団は南下する進路を変針し戦況を見守っていたが、両軍空母の相互に損害があり、八日午後には第4艦隊長官からモレスビー攻略無期延期の指令が入った。幸いにも船団は無傷で反転し、五月九日夕刻ラバウルに帰還上陸した。
ラバウルに帰還した支隊は、五月一九日、新たに発せられた戦闘序列によって第17軍(司令官・中将百武晴吉)の隷下に入り、再度のモレスビー攻略を準備していたが、六月上旬のミッドウェイ敗戦によって海軍勢力が大きく滅衰したので、海上進攻は望めなくなった。
〈ポートモレスビー陸路攻略〉
大本営はその後もモレスビー攻略の企図を捨てず、第17軍に陸路進攻の偵察を命じた。このころ南海支隊には歩兵第41連隊(第5師団隷下でマレー作戦に参加)・独立工兵第15連隊・臨時編成輜重二個中隊・高砂義勇隊(台湾高砂族で編成)などが配属された。当時この地域の兵要地誌は皆無で、海軍航空隊の撮影した断片的航空写真が唯一の資料であった。この陸路進攻作戦は標高三、〇〇〇メートルを超え常時白雪を戴くオーエン・スタンレー山系を踏破し、行程三六〇キロメートルに及ぶもので、駄馬道さえない小径の担送補給計画が最大関心事であった。
南海支隊長は独立工兵第15連隊長の指揮する先遣隊を七月二一日ブナに上陸させ、道路の補修と軍需品の集積を行うとともに、進路の偵察を命じた。先遣隊は海岸からサンボまで六〇キロメートルを自動車道に改修し、支隊主力の上陸を待った。また海軍の設営隊はブナに戦闘機用飛行場を設定し、八月一六日には使用可能となった。支隊長は主力を率いて同月一八日バサブア(ブナ西方一五キロメートル)に上陸し、スタンレー山系の険を目指して前進を開始した。武器弾薬の他に各人約七・五キログラムの主食を携行しなければならず、装具も合わせた総重量は五〇キログラム近くになった。
八月三一日、イスラバの堅陣を突破した支隊は、41連隊主力を追撃隊とし、濠軍累次の抵抗と困難な地形を克服して、九月五日には標高二、〇〇〇メートルを超えるスタンレー山系の分水嶺に進出、一二日にはイオリバイワ(モレスビー東北五〇キロメートル)に拠るほぼ同等の濠軍を撃破してこれを占領した。しかしこのころ戦線の伸長で補給は滞りがちとなり、携行した米は既に乏しく、一日の定量を一合(一五〇グラム)に節約しなければならない状態になっていた。
これより先、第17軍司令官は南海支隊に対し、モレスビーに向かう前進を控制していた。これは新しく増援する兵団を海路この攻撃に参加させ、一挙にモレスビーを攻略する計画があったからである。しかしこの計画はガダルカナル島の戦況悪化に伴い実現せず、更に配属されていた歩兵第41連隊は、ブナ地区への連合軍攻撃企図に備えて抽出転用された。支隊に対する補給はその後も好転せず、九月二三日、支隊は山系北側のイスラバ、ココダ付近に後退集結せよとの軍命令を受けた。二六日開始された支隊の後退は幸いにも濠軍に察知されることなく行われたが、食糧不足で体力の衰えた将兵には苦難の行軍であった。支隊長は144連隊第2大隊をスタンレー支隊として分水嶺に残置し、主力は一〇月四日、ココダに集結を終わった。大部隊の集結により付近で調達できる芋や果実は皆無となり、後方輸送に従事していた現地人なども多くが散逸して補給はますます悪化した。
支隊の後退を察知した濠軍は次第に追尾して我が軍に迫り、一〇月下旬、遂にスタンレー頂上線を放棄するに至った。軍から確保せよと命じられていたイスラバ、ココダの線も防禦に適さず、南海支隊は更に後退してオイビ付近に陣地を占領して濠軍を迎撃することにした。一度ブナ地区の警備についていた41連隊も再びこの戦線に招致され、一一月一日から全力をあげて防戦に努めたが、濠軍は次第に支隊の背後にも浸透し、退路を遮断されるとともに全滅する中隊もあった。
〈海岸線へ撤退集結〉
一一月一〇日、南海支隊長は全般の情勢を判断し、完全包囲に陥るより先に兵力を海岸線に撤退し、揚陸点で最後の防御をする決心をした。命を受けた諸隊は濠軍の間隙を衝いて脱出反転を始めたが、戦傷病者の中には体力の衰えた戦友に担送能力のないことを覚り、自決する者も相次ぎ悲惨な場面が現出した。この反転中、支隊長堀井少将は水没戦死し指揮系統は混乱した。このため独立工兵第15連隊長が支隊の指揮をとり、ギルワ地区に支隊兵力を集結して防御態勢をとった。ブナ地区は、一一月一九日から新たに上陸した米軍の猛攻を受け、同地の陸海軍守備隊はこれに応戦した。この米軍は同時に南海支隊の防御するギルワ地区にも奇襲攻撃をかけ、144連隊の軍旗近くにまで侵入したが、連隊の将兵はよくこれを撃退した。
ブナ・ギルワ・バサブヤ各守備隊の苦戦に、海陸軍の戦闘機も反覆出撃して支援したが大勢に変化はなく、バサブヤは一二月八日、ブナは翌一八年一月二日、遂に玉砕するに至った。144連隊に着任した新連隊長(大佐山本重省)は部下を掌握することもできないままに戦死した。
新南海支隊長(少将小田健作)は一二月二〇日、この惨状を極める戦場に到着した。ガダルカナル作戦のため海上輸送は絶無となり、ギルワ守備隊全地域が米軍砲兵の中距離射程内に置かれ、兵員の全部が患者となっていた。米・濠軍の攻撃はいよいよ激しく、一月一六日には我が軍の保持する海岸線はわずか二、〇〇〇メートルに圧迫された。支隊長は軍司令部の指示により、一月二〇日、西方のクシム河々口への転進を命令した。行動不能の患者は陣地内に残置せざるを得ず、ここでもまた多数の自決者があった。各部隊は路なき密林や湿地帯を越えて進んだが、その行程は遅々たるものであった。二月初めころにはクシム河口に集結したが、その兵力はギルワ出発時の半ばに過ぎなかった。支隊長小田少将は部隊の転進開始を確認した後、陣地内で自決し、部下英霊とともに同地にとどまった。
転進部隊は西方友軍部隊の援護下にマンバレー地区に退却し、四月にはサラモアへ夜間の大発(上陸用舟艇)航行によって輸送され、この地で支隊の任務を解除された。当初編成人員と補充人員合計の七三%強を失い、残人員は二、〇〇〇名に満たないものとなっていた。
昭和一八年六月、支隊は第18軍の隷下を離れ、人員補充の後母隊である第55師団に復帰するため、七月下旬ラバウルを出発した。船団は台湾の高雄に寄港したが、九月二日、歩兵第144連隊主力の乗船した宏山丸は米潜水艦によりその港外で撃沈された。支隊は再びこの地で人員装備の補充を行い、その後バンコクに上陸、一二月には陸路ビルマのアキャブ戦線に到着し師団長の指揮下に復した(〈第二次アキャブ作戦〉の項参照)。
歩兵第122連隊(南洋第1支隊)
昭和一六年(一九四一)、米英に対する開戦が予測される情勢になったので、軍は極秘裡に動員を行い、戦闘兵力の増強を図った。
歩兵第122連隊は、占領地警備を目的として創設された第65旅団(兵団符号「夏」)の隷下として松山の留守部隊で編成に着手し、同年一一月八日編成を完結した。連隊は歩兵二個大隊(大隊は歩兵三個中隊・機関銃一個中隊)に野砲中隊・通信中隊・連隊砲小隊で構成され、正規編制の約半分の軽量編成の部隊であった。
第65旅団は、司令部・工兵隊・野戦病院及び第141連隊が福山で、第142連隊が松江で編成され、後方輸送機関は保有しないものとなっていた。
連隊(初代連隊長・大佐渡辺祐之介)には真新しい軍旗が授与せられ、一一月一五日未明、機密保持のため見送る人もなく、ひそかに征途に就いた。
旅団は先ず台湾に集結することを命じられ、連隊は同月二二日、基隆に上陸、列車輸送により主力は台中に、一部は嘉義に分駐し、熱帯地域の戦闘に備えて猛訓練を行った。
昭和一六年一二月八日、我が国は太平洋戦争に突入し、比島においては第14軍がマニラに向け進撃を開始した。一二月三〇日、第14軍に増加を命じられた旅団は高雄を出港し、翌一七年元旦、ルソン島リンガエン湾ビガン付近に上陸、先ず北部ルソンの占領した飛行場の警備についた。このころ米比軍はマニラを放棄してバタアン半島に後退したので、第14軍は隷下の第48師団を抽出し、ジャワ進攻作戦に転用することにした。第65旅団はこのため急に第一線に起用され、退却する米比軍をバタアン半島に急追する任務が与えられた。旅団は米比軍撤退の際の橋梁破壊に苦しみながら、北部ルソンから炎熱の中を昼夜兼行でバタアン戦線に急進した。
〈第一次バタアン攻撃〉
一月九日、旅団主力(歩兵第122連隊を除く)はバタアン半島中央山岳の東側に展開し、米比軍の拠る高地の攻撃を開始した。この作戦は軍司令部が敵情を過小評価するという重大な判断過失を冒したため、二個師団強の守備している前進陣地に対し、はるかに劣勢な兵力(歩兵二個連隊基幹)で攻撃を仕掛けたことになり、苦戦を強いられて戦況はほとんど進展しなかった。
この攻撃のとき、歩兵第122連隊(第1大隊長の指揮する2個中隊は北部ルソン警備のため残置)は右側支隊を命じられ、デナルピアン―オロンガポ道を西進し、半島の西海岸沿いに進攻することになった。この道路は米比軍により徹底的に破壊されていたため、せっかく配属された野砲兵大隊は随伴することができず、やむを得ずこれを残置しなければならなかった。北部ルソンから連続強行軍の極度の疲労に耐えて、一〇日午後には西海岸のオロンガポに進出した。渡辺支隊長は同地の沖スビク湾に浮かぶウイント要塞(グランデ島上)の守兵が撤退したことを察知し、独断でこれを占領する決心をし、一二日、民船を利用して上陸を敢行、四〇センチ加農砲ほか砲一八門、弾薬・燃料多数をろ獲する戦果をあげた。
軍司令部もようやく第65旅団主力正面の苦戦を知り、西海岸で戦況が進展した右側支隊方面から戦果を拡大するため、木村支隊(第16師団の歩兵団長指揮する歩兵第20連隊基幹)をこの戦線に投入することにした。このため連隊は木村支隊の指揮下に置かれることになったが、その到着を待つことなく南進を開始した。海岸地帯は泥に腰を没する大湿地帯、山地は千古の密林で辛うじて駄馬が通じる小径があるに過ぎず、戦闘資材は舟筏によって海上輸送をしなければならなかったが、一六日にはモロンに拠る米比軍の守備陣前に進出した。一五センチ榴弾砲を有するこの陣地は周到な射撃準備がなされていて、独力攻撃する連隊の前進を阻んだが、一七日未明からの一斉攻撃により夕刻にはモロンに突入した。夜に入ると米比軍はその南方の主陣地から曳光弾の射網を構成し、我が奇襲を警戒した。
翌一八日、木村支隊がこの第一線に進出して来たので連隊はその指揮下に入った。連隊の将兵は先の強行軍以来休む間もなく、糧秣の補給は絶え疲労の極に達していたが、木村支隊の右翼隊を命じられると、直ちに進撃に参加した。米比軍の主陣地は鉄条網に地雷を配し、予め一五榴などの観測標定がなされていたもので、無線の電波を発しても射弾が集中する有り様であった。支隊は多大の損害を被りながらも力攻を続け、二五日に至ってようやく陣地の一角を奪取することに成功した。このころ木村支隊の一部海上機動兵力(歩兵第20連隊第2大隊)は舟艇によって米比軍後方に敵前上陸を敢行した。この奇襲作戦は守備軍に動揺を与え、浮き足立った守兵の後退気配が看取された。支隊は直ちに追撃に移り、バガック付近に進出、更に戦果を拡張しようと努めた。この時我が軍は、バガック南方の陣地が、オリオン―サマット山北麓―バガックと東西一連の米比軍主抵抗陣地であることに気付いていなかった。支隊の左翼隊(歩兵第20連隊長の指揮する第3大隊)は突進隊となって二九日、この陣地を突破し、陣内深く突進したが、翌日にはその突破口を閉塞され、包囲されて孤立無援となった。右翼隊122連隊の中、左翼隊に連繋する第3中隊も陣内に深入り包囲され、中隊長以下一三〇名戦死、生存わずか二〇名という打撃を受けた。
更に先に陣地後方に敵前上陸した20連隊第2大隊も逐次新鋭米比軍に圧迫され、上陸地点に辛うじて防戦していることが判明した。支隊長はこの大隊を増援補給する目的で、新たに同連隊第1大隊及び補充弾薬食糧を舟艇によって急派することにした。大隊は二月一日深夜、守備陣地からの激しい砲火を冒して上陸に成功したが、第2大隊と合流することはできなかった。両大隊とも次第に戦車を伴う反撃に遭い、肉薄攻撃を行うなど敢闘したが及ばず、二月一〇日前後に相次いで玉砕した。20連隊長揮下の突進隊も甚大な損害を被っていたが、残存する兵員を集め、二月九日返転を開始し、一五日帰還することができたが、同連隊の戦力は事実上潰滅した。
第65旅団主力正面においても、一月二四日夕、一度はカラギナン川南岸の前進陣地を抜いて追撃に移ったが、二七日以降はオリオン―サマット山北麓にわたる主抵抗陣地に阻まれて再び攻撃は挫折した。この時初めてこれが米比軍新鋭兵団による半島の主防御線であることを知った。これら第一線部隊の惨状と戦力の低下を見た軍は二月八日、一且この攻撃を中止することを決定した。連隊は同月一九日、木村支隊の配属を解かれ、旅団に復帰したが、この一連の戦闘において三五〇名を下らぬ戦死者を出していた。旅団は封鎖陣地を占領して米比軍と相対し、戦力の回復に努め次期攻撃に備えた。連隊にも兵員の充足が行われるとともに、さきに北部ルソンに残置した第1大隊長が第1中隊を伴って復帰し、戦力の回復に努めた。(第2中隊はルソン島東北カガヤン州警備に残留)
〈第二次バタアン攻撃〉
軍は新たに新鋭兵団を第一線に増加し、四月三日朝から第二次の攻撃を開始した。地上では右から第16師団・第65旅団・第4師団と併列し、東海岸には永野支隊(「歩兵第62連隊」の項参照)の突進を用意した。今度は軍司令部が敵情を過大評価し、陸軍開闢以来の砲爆撃を準備した。三〇〇門の火砲は一万四、〇〇〇発の砲弾を、一〇〇機の重・軽爆撃機は八〇トンを超える爆弾をこの陣地に集注した。その威力の前に米比軍が数週間を費して構築した野戦陣地はたちまち瓦解した。第一線各兵団は砲爆撃の効果に乗じて第一陣地を抜き、次々と縦深の抵抗を排除してサマット山に迫っていた。この時、第65旅団は隠蔽錯雑したジャングルや深い溪谷を踏破して突進し、右翼隊の122連隊は六日昼ころ他兵団に先んじて六号道路と八号道路の交差点を奪取、これを確保した。この地点は山岳ジャングルの中で兵力運用に欠かせぬ要地であった。米軍側史料によれば、交差点付近にあった米比軍のD防御区司令部は後退を余儀なくされ、東北方で抵抗中の隷下二個師団との通信連絡が途絶して混乱に陥っている。
旅団の要地占領により米比軍の戦意は急速に衰え、白旗を掲げ投降するものが相次いだ。各隊は付近を掃討するとともに、七日には夜襲をもって一五四二高地周辺に進出した。六日以降、マリベレス山頂攻略を命ぜられた122連隊第2大隊は、熱帯樹の生い茂った険しい山や崖を苦難を重ねて踏破し、九日夕、遂に標高四、六六〇フィートのマリベレス山を占領した。この日、ルソン軍司令官キング少将が降伏し、米比軍の組織的抵抗は終了した。旅団はその後サマット山付近の敗残兵を掃討し、その北西地区に兵力を集結した。
連隊は再び北部ルソンに移駐し、イロコス・アブラ地区の警備につき、本来の任務に復帰した。
〈マーシャル諸島の守備〉
昭和一七年(一九四二)一一月、第65旅団主力は第18軍の隷下となり、東部ニューギニアへ転進した。この時、歩兵第122連隊は比島に残り警備任務を続行した。
昭和一七年六月、ミッドウェー海戦の敗北を転機に、米軍の反攻が開始された。八月にはガダルカナルに上陸した米軍との死闘が繰り広げられたが、翌一八年二月には遂に撤退のやむなきに至った。大本営の南方戦線再編成により、連隊はマーシャル諸島へ配置されることになったが、このとき渡辺連隊長が転出し、後任に大佐・大石千里が着任した。昭和一八年八月二四日、マニラで海軍艦艇に乗船した連隊は、トラック島を経由して九月七日にはクェゼリン島に入港した。連隊は海軍第6根據地隊に配属され連隊本部・第6中隊・砲兵隊一個小隊はクェゼリン島に、第1大隊・連隊砲小隊はミレ島に、第2大隊(第6・第7中隊欠)。はウオッゼ島に、第7中隊はマロエラップ島に分散配置され、それぞれ各島の海軍警備隊司令の指揮下に入った。これら守備隊は全力をあげて野戦築城の作業に取り組んだが、珊瑚砂質のため深い掩蓋構築物や坑道の掘開はできなかった。
一一月一六日、連隊は第65旅団隷下の編制を解かれ南洋第1支隊に改編された。このため兵員は一度全員現地除隊し、即日新しい支隊に動員応召するという手続きが行われた。また軍旗は海軍機に便乗して内地に輸送、奉還の手続きをとった。このころ、ギルバート諸島の失陥でマーシャル諸島は太平洋戦線の最前線となっていた。
一二月に入って、海上機動第1旅団のマーシャル進出に伴い、連隊主力(第2大隊欠)はミレ島に移り、海軍第66警備隊司令の指揮下に入った。このときギルバート逆上陸部隊として待機中であった歩兵第107連隊第3大隊基幹の部隊が連隊長の指揮下に入れられた。第2大隊(長・少佐古木秀策)はヤルート島に集結を命ぜられ、一九年一月中旬、本部と半数の兵力はヤルート島に到着したが、ウオッゼ・マロエラップに残した半数の第二陣は、それ以降海上移動が不可能となり、そのまま終戦に至った。当初連隊本部とともにクェゼリンにあった第6中隊は、ギルバート逆上陸の任務が与えられていたが、同島失陥のため一八年一一月ヤルートに進出しており、大隊長の指揮下に復した。またクェゼリン残留兵力の一部は小舟艇でヤルートに向い進出中、消息を絶った。海上あるいは途中の小島で米軍の攻撃により玉砕したものと判断される。一月三〇日、ミレ島は二〇〇機余の米軍機の空襲を受けた。各島基地の我が航空隊は既に戦力を失い、地上部隊が機関銃で迎撃したが大きな被害が続出した。この空襲に引き続き、二月一日、クェゼリン・ルオット島に米海兵隊が上陸を開始した。ウオッゼ島からヤルート島に集結するため、クェゼリン島で便船待ち中の第5中隊の一個小隊は、海軍守備隊とともにこれを迎撃し、肉弾戦を展開して玉砕した。
その後ミレ・ヤルート両島とも連日艦載機の来襲を受け、施設は破壊され補給も途絶した。昭和一九年三月末には非常用食糧数日分を残して食糧は皆無となり、魚・椰子の実・野生の草木で生命をつないだが、栄養失調やパラチフスによる死亡者が多発した。
八月中旬、米軍機の空襲が突然激化し、その数は延べ二、七〇〇機に及んだ。残存基地施設は根こそぎ破壊され、生い茂っていた椰子林もほとんど倒壊した。米軍は上陸することなくこれらの基地を無力化したもので、盛んに降伏を勧告する伝単(ビラ)を散布した。死と対決した地獄の毎日を、生存将兵はなお戦意を失うことなく、自活態勢で収獲されたわずかの食糧も公平に分配して耐え続け、終戦の日を迎えた。この間、マーシャル群島警備作戦において支隊(配属部隊を含む)は二、〇〇〇名に及ぶ戦・病死者を出していた。同年九・一〇月にわたり島を撤収し復員した。
山砲兵第31連隊
昭和一八年(一九四三)七月、第40師団山砲兵連隊は新設第31師団に隷属替えとなり、山砲兵第31連隊となってビルマに転戦することになった(第40師団編成の縮小の項参照)。これは昭和一七年末ころから英印軍の反攻の徴候が表われはじめ、各方面から急速に兵力を抽出集中する策の一環として行われたものであった。連隊は中支の咸寧を出発し、サイゴン・バンコクを経て九月下旬、ビルマのペグー付近に集結、第31師団(兵団符号「烈」、長・中将佐藤幸徳)の隷下に入った。
昭和一九年三月一五日、インパール作戦が開始され、師団もチンドウィン河を渡河して、四月六日には要衝コヒマ(インド領)を占領した。初め三週間で終了する予定の作戦が、英印軍と連日死闘を繰り返して二か月、弾薬糧秣の微弱な補給に師団の戦力は惨めに低下した。ここに至って師団長はコヒマ撤退を決意した。六月二日からチンドウィン河に向って撤退が開始されたが、連隊の砲搬送の馬匹もそのほとんどが倒れ、雨期泥濘の悪路を栄養不足で衰えた兵士による人力搬送が続けられた。この退却行は患者を先行させる措置がとられたが、独歩困難な傷病者の大部分は自決の途を選び、先行した患者の中にも沿道の密林内に力尽き倒れる者、濁流に呑まれて消息を絶つ者が相次いだ。気力だけで砲を搬送し、八月中旬には辛うじてチンドウィン河畔に達することができた。
その後師団は方面軍の計画したイラワジ会戦に参加の命を受け、翌二〇年一月初旬、マンダレー西方のイラワジ河畔に後退して防備に就いた。その後ビルマ戦線の崩壊に伴い、三月中旬にはキャウセ(マンダレー南方五〇キロメートル)に、五月からは苦難の行軍の末マルタバン(モールメン対岸)に集結、終戦を迎えた。
南洋第6支隊
昭和一八年一二月初め、南方戦線再編成の初期の動きとして、松山で南洋第6支隊(支隊長・大佐松尾勇太郎)が編成された。島しょ守備を目的としたこの部隊は歩兵二個大隊(大隊は歩兵三個中隊・機関銃及び歩兵砲各一個中隊)及び久留米で編成された戦車一個中隊で構成されていた。松山で編成された歩兵大隊は、将校・下士官(分隊長以上一二六名)のみという変則編成であったが、これは当時既に逼迫していた船舶輸送力にかんがみ、船腹占有を軽滅し、現地滞留兵員をもって編成を充足する狙いであった。
支隊は一二月二九日、宇品を出港し、翌一九年一月一二日、パラオに上陸、パラオ諸島の防衛準備に着手したが、予定された兵員は戦局の急迫に伴い他に転用せられておらず、依然幹部主体という変則のままであった。
このころ連合軍は東部ニューギニアを手中に収め、ダンビール海峡(ニューギニアとニューブリテン島間)を突破して、我が絶対国防圏の一環である西部ニューギニアに迫ろうとしていた。このため軍はウェワク・アイタベなど中部ニューギニアの要衝の防衛を強化するとともに、ホーランジヤに主力戦闘兵団の集結を企図した。一月一九日、南洋第6支隊(戦車中隊を除く)もホーランジヤに転進すべき大本営命令に接した。
支隊長は第1大隊を先遣隊として二月二六日、自らも第2大隊を率いて同二九日、パラオを出港したが、両梯団とも執ような米潜水艦・魚雷艇の追尾を受け、三月三日、支隊長梯団の船は雷撃を受け海没した。このとき松尾支隊長以下四五名が戦死し、ホーランジヤに到達した者は二四〇余名(将校五六名、下士官一七四名、兵一二名)であった。支隊は同地所在の上級指揮官の指揮下に入って四月二二日の米軍の上陸を迎え撃った後、逐次西方サルミ地区に転進し、食糧不足とマラリヤに苦しみながら終戦を迎えた。
南洋第2支隊
南方戦線再編成のため、関東軍から抽出派遣された兵力の中に、南洋第2支隊も含まれていた。この支隊は本来関東軍第4独立守備隊(司令部・牡丹江)の中の第19大隊(駐屯地・下城子)・第20大隊(駐屯地・寧安)・第21大隊(駐屯地・延吉)をもって構成され、昭和一八年一一月、それぞれの駐屯地において南方派遣の支隊(長・中将原田義和)編成を完結した。これら各大隊はもともと東北地方の壮丁が主体であったが、昭和一七年一月入隊の兵員は四国地方の壮丁で占められ、とりわけ本県人の比率が重く、その数五〇〇名を下らなかった模様である。
支隊は昭和一八年一二月一四日、釜山を出航し、駆逐艦・駆潜艇の護衛の下に航行を続け、翌一九年一月三日、クサイエ島(現コスラエ州)に上陸した。同島には先に上陸した海軍第42警備隊・陸軍甲支隊の一部(歩兵第107連隊長の指揮する一個大隊)などがあったが、支隊はこれら部隊と共に同島の守備に就いた。クサイエ島は面積一一六平方キロメートル、当時約二、〇〇〇人の原住民がいたが、日本の統治下にあったため極めて好意的であった。
米軍はこの島に対しても上陸することなく、無力化する策をとり、我が海上補給を封鎖するとともに艦砲射撃と爆撃を反覆した。支隊長はあらかじめ原住民を予測される戦闘区域外に疎開させていたので、これらの被害は皆無に近かった。潜水艦による主食の補給が一回行われたが、食糧事情は次第に窮迫し、昭和一九年末には一日当たり甘藷三五〇~五〇〇グラム支給にまで低下した。このため将兵の体重は平均一二キログラム減少し、栄養失調患者が続出した。しかし自活態勢整備の甲斐があって、同二〇年六月にはほぼ食糧自給の目途がつくに至った。このような苦境の中にあっても軍紀は厳正で、住民との間にもトラブルは発生しなかった。
独立歩兵第333大隊(南洋第5支隊)
昭和一八年九月末、大本営は南東方面の現戦線を持久する間に、後方要線に「絶対国防圏」と呼ぶ新作戦準備を完成する方針を採択した。この要線は東部蘭印から西部ニューギニア、内南洋中西部を経てマリアナ諸島に至るものであった。この新戦線に配備するための兵力の転用が関東軍からも抽出して行われたが、当初は極力関東軍の戦力低下につながらないよう配慮された。
歩兵第22連隊(西東安に駐留)からも第1大隊(長・大尉中島平吾)が当時の建制のまま抽出され、独立歩兵第333大隊と呼称を変え第7派遣隊として南方に向かうことになった。大隊は同第334大隊(歩兵第32連隊より抽出)とともに一九年一月、密山を出発して南方に向かったが、企図を秘匿するため訓練を偽装してロ号演習と称した。釜山から輸送船に乗船し、高雄・パラオ・サイパン・グアムを経由して航行したが、同年二月始めにはクエゼリン・ルオット島の守備隊が玉砕し、同月一七日にはトラック島が大空襲を受けるなど、絶えず空と潜水艦の脅威にさらされての航海となった。幸いにも輸送船はこれらの攻撃を受けることなく、四月二三日、メレヨン島(カロリン群島、トラック島西方九〇〇キロメートル)に上陸し独立歩兵第334大隊とともに南洋第5支隊となった。同島には約七、〇〇〇名の陸海軍諸隊が集結し、独立混成第50旅団(長・少将北村勝三)が編成されて守備に任じた。第333大隊はこの環礁の中のオッタカイ島に陣地を構築し米軍の上陸に備えた。
米軍はこの島に上陸することなく、基地を無力化する策を採った。大隊が島の配備に就いて以降終戦までの五〇〇日の間、空襲は二五五回に及び、艦砲射撃も加わって諸施設の被害は甚大なものがあった。旅団司令部所在地のフララップ島の飛行場は滑走路が無数の弾痕の荒地と化し、早々に使用不能となった。
米軍は糧道を絶つ作戦をとり、我が軍は飢餓との戦いに明け暮れる羽目に追い込められた。潜水艦による主食の補給が数次にわたり行われたが、多数の兵員には充足せず、一日当たり七二〇グラムであった米の給与は次第に減量され、遂には七〇グラムにまで低下した。不毛のサンゴ礁に苦心の末開墾した自活農園に対して、米軍機は容赦なくガソリンを散布して焼き打ちを行った。島内の昆虫・トカゲ・ネズミは捕食されて絶滅し、ヤシの実を腐敗させてウジを培養し、露命をつなぐ者もあった。兵員の健康状態は低下の一途をたどり、戦技訓練はもとより、陣地構築作業にも堪えられない者が多くなり、戦わずしてその戦力は無力化された。
独立混成第50旅団司令部の統計によれば、上陸当初の兵員数三、二〇五名のうち、戦死一三二名、戦病死二、二八七名、生還七八六名と記録されている。終戦とともに米軍の給養を受け、重症患者は別府温泉で保養し、健康回復に努めた後故郷に復員した。
独立混成第48旅団
第24師団隷下の歩兵第22連隊から第1大隊が南方に抽出派遣されたのに続いて、関東軍第1・第11師団からも同様の兵力の抽出が行われた。このときも北方戦備を極力崩すことなく、派遣部隊にも優秀な人員装備を具えるようにと苦心が払われた。この部隊は第6派遣隊と呼ばれ、昭和一九年(一九四四)二月下旬、各駐屯地において編成を完結した。その編制は次の通りで、総兵力は五、一〇〇名であった。
派遣隊長・少将重松潔(第11歩兵団長)
第11師団より 歩兵三個大隊・山砲一個大隊・工兵一個中隊
第1師団より 歩兵三個大隊・野砲一個大隊・工兵一個中隊
派遣隊は多数の戦友の見送りを受けて駐屯地を出発し、釜山において夏服が支給された後、三月三日同港出港、一度東京湾に寄って船団を組み、同月一二日、再び南下した。この船団は出港翌早朝には早くも潜水艦の雷撃を受け、護衛艦や僚船が撃沈されるとともに派遣隊の船も損害を受けた。輸送船は一たん東京湾に退避した後再び南下し、三月二〇日無事グアム島に到着、上陸した。
当時グアム島には既にマリアナ地区集団(長・第29師団長中将高品彪)として第29師団主力と海軍部隊約八、〇〇〇名が守備に就いていた。第6派遣隊は師団戦車隊の一部の配属を受け、その主力をもって島中央部西海岸の、一部をもって同東海岸の防衛を担当することになった。また歩兵・山砲の各一個中隊はロタ島(グアム東北六〇キロメートル)に移駐し同島の守備に就いた。防備は上陸軍を水際に撃滅することに徹し、資材の不足を補うため自然の洞窟を利用した横穴式陣地が主体に構築された。またりーフを活用した水際障害物も併行して設置された。
五月二二日、第6派遣隊は改編され、第11師団関係部隊をもって独立混成第48旅団が、第1師団関係部隊をもって独立混成第10連隊が編成された。
上陸当初は華々しい空中戦や艦船攻撃を行っていた海軍航空機は次第に消耗し、七月初めには飛行可能機は絶無となった。制空権を完全に掌握した米軍は、七月七日のサイパン占領の余勢を駆ってグアム島に対する砲爆撃を強化した。二週間にわたるこの砲爆撃で、米軍の参加艦艇は戦艦六、巡洋艦九、駆逐艦五七、砲艦一八、空母一五、延べ発艦機七、五〇〇、投下爆弾七、〇〇〇トンに及んだ。これら膨大な火力のために海岸の椰子林はほとんど裸になり、レーダー施設は全部損傷し、野戦陣地の大部分は破壊された。しかし洞窟横穴の活用と適切な回避疎開によって人員・兵器の損害は最少限に止めることができた。
七月二一日早朝、激烈な支援砲爆撃の下に米軍の上陸が開始されたが、その主攻撃は48旅団正面に指向されていた。第一線守備隊は猛烈な砲撃に屈することなく対舟艇射撃を開始し、上陸用舟艇・水陸両用戦車を次々と破壊した。しかし所在を発見された我が重火器もまた集中火を被り、次第に制圧されていった。上陸した米軍は歩兵と戦車の協調態勢を整えた後前進を開始したが、陣地を死守する第一線将兵は白兵戦・対戦車肉薄攻撃を繰り返して阻止に努めた。この日の戦闘において旅団は歩兵部隊の六分の一、砲兵部隊の三分の一を失ったが、米軍側も沖合いの病院船にひっきりなしに傷兵を後送する様が望見され、将兵の士気は依然旺盛であった。
夜に入って小部隊ごとにそれぞれ橋頭堡に対する夜襲を決行したが、我が常套戦法を警戒していた米軍の照明弾や艦艇のサーチライトに企図を暴露し、水陸両用戦車からの掃射を浴びて挫折し大きな損害を被った。
二二日以降も我が諸隊は巧みに地形を利用し、夜間攻撃も無謀な突入を戒めて持久抵抗の態勢に入った。
この間米軍は逐次上陸兵力を増加し、以後の攻勢を準備中で、時日の経過は我が軍に不利となることが判断された。このためグアム島駐在の全軍を挙げて二五日夜、明石湾方面の米軍橋頭堡に全力攻勢を行うことが決定された。二五日昼間には戦車群が旅団の固守する高地に進入し、その蹂躙に任せる状態となった。しかし夜に入って戦車群が後退したので、二四〇〇を期して所命の如く総反撃が決行された。折しも豪雨の中を各隊とも果敢に突撃に移ったが、この中には入院中の患者や抜刀隊を組織した邦人男子も参加していた。静寂の戦場は一転して叫喚の巷と化した。照明弾は戦場を昼間と化し、優勢な艦砲射撃と地上火器が集注した。突撃隊は戦友の屍を越えて前進し、随所に手榴弾戦・肉弾戦を演じたが衆寡敵せず、多大の損害を被って全力攻勢は再び不成功に終わった。
旅団長は残存兵員を集結し、要点高地の死守を指示したが、翌二六日には数十両の戦車の包囲を受け、午後には旅団長以下司令部の人員は全員玉砕した。また第一線に進出して指揮に当たっていた高品師団長も二八日に戦車群の包囲を受け、北方に脱出中戦車砲弾を受けて幕僚と共に戦死を遂げた。残存兵員は予め指示された島北部での遊撃持久戦に移行するため北進を開始したが、多数の負傷者を抱えその行進は悲惨であった。米軍は周到な準備を整え、我が撤退援護陣地を徐々に席巻しながら、集結地と思われる地点にはなおも激しい艦砲射撃を加えた。対戦車兵器が全く欠乏した抗戦はその都度もろくも突破され、米軍は八月一二日、島の北端に進出、翌一三日にはグアム島全島の占領を宣言した。
米軍が島北部に進撃する間、残存将兵の中密林地帯に潜入した者、あるいは島南部の山岳地帯に配備残置された者は数千人に及んだ。これら将兵は島内の動植物を採取し、海水から塩を作るなど自活の途を拓きながら、密林内で遊撃戦を継続した。米軍も掃討を行うとともに投降を呼びかけたが、巧みに移動しながら遊撃戦を行う日本兵に手を焼き、遂には掃討を断念した。終戦後の昭和二〇年九月四日、米軍の指定した地点には、密林を後にした一、三〇〇の将兵が集結した。
昭和一九年以降の郷土関連部隊
〈第111師団〉
昭和一九年(一九四四)八月、在満師団臨時編成(軍令陸第八二号)が行われ、関東軍の国境(独立)守備隊などを改編し、新たに三個師団と二個独立混成旅団が編成された。第111師団(兵団符号「市」、長・中将岩崎民男)はこのとき綏陽県綏陽において編成を完結したが、その補充業務は留守第55師団長が担当することに定められていた。
ビルマの第55師団に対する人員補充は、海上輸送のひっ迫によりこのころは実施不可能となっていた。
師団は歩兵三個(243~245)連隊及び師団砲兵・工兵・通信・輜重兵隊その他で構成され、新編成での訓練に邁進した。翌二〇年四月、師団は朝鮮済州島に移駐し、第58軍(司令官・中将永津佐比重)の隷下となって、同島水際防御基幹師団として西方海岸主陣地帯の防衛に就いた(「第17方面軍作戦準備史」)。
〈第120師団〉
昭和一九年一二月、臨時編成(軍令陸第一五九号)により東寧県老黒山ほかにおいて編成を完結したが、この師団の補充業務も留守第55師団長の担当となっていた。師団(兵団符号「邁進」、長・中将柳川真一)の編制は第111師団と同様で、歩兵は三個(259~261)連隊であった。
師団は二〇年五月、朝鮮の釜山・慶山地区に移駐し、その後作戦計画の変更により済州島に増援配備の準備中終戦を迎えた。終戦後は260連隊が元山に、261連隊が平壌に派遣されて居留民保護に当たったが、平壌の261連隊はソ連軍に武装解除され、遠くソ連領内に抑留される羽目になった(「第17方面軍作戦準備史」)。
〈第121師団〉
昭和二〇年二月、更に在満師団臨時編成(軍令陸甲第九号)が行われ、国境守備隊その他部隊を改編し、新たに八個師団と四個独立混成旅団が編成された。第121師団(兵団符号「栄光」、長・中将正井義人)はこのときハルビンにおいて編成を完結したが、その補充業務は中部軍司令官が担当し、四国の留守隊に業務が課せられた。構成は前同様で、歩兵は三個(262~264)連隊編成であった。
師団は同年五月に朝鮮に移駐、六月には済州島の第58軍の隷下となって、同島東方地区に攻勢兵団として配備に就いた(「第17方面軍作戦準備史」)。
これら三個師団は、終戦とともにソ連に抑留された部隊を除き、昭和二〇年一〇月から一一月にかけ佐世保に上陸復員した。
〈登建部隊〉
昭和二〇年一月、善通寺の留守第55師団管理の下で登建部隊が仮編成された。名称の「登」は南支那派遣第13軍の兵団符号、「建」は福建省の一字を取ったもので、当時福州付近にあった独立混成第62旅団を増強し、これを師団に格上げする目的の兵力であった。部隊は独立歩兵四個大隊・砲兵三個中隊・工兵二個中隊その他の構成であった。一月一八日、高松を出発した部隊は岡山―下関―博多…釜山―京城―奉天―天津―徐州―上海と一〇日余を費して上海に到着した。その後は海上輸送による福州への前進の機をうかがったが船舶不足のため実現せず、わずかに歩兵一個大隊のみが輸送せられて独立混成第62旅団に合流することができた。残余の部隊兵員は上海付近において編成中の第161師団要員に充足されることになった。同師団は南満州に転用の予定であったがその準備中終戦となり、南京警備などに従事した後復員した。
このころ陸軍の徴集補充業務の機構上松山での編成は行われず、県人壮丁・召集者は他三県の編成部隊に分散入隊していた。
郷土の戦備
太平洋戦争が始まってからの郷土の戦備については、終戦の際の書類焼却などにより詳らかにしない点が多い。以下残存資料によって判明した範囲を記述することにする。
(1)海軍関係
〈海軍人事部の設置〉
昭和一二年(一九三七)七月、高松地方海軍人事部が設置され、その愛媛県関係の出先事務所が松山市出渕町に置かれて、海軍兵員壮丁の徴集業務に当たった。これは昭和二〇年四月、松山地方海軍人事部と改められた。
〈豊後水道の防備〉
豊後水道海面の防備は呉鎮守府隷下の佐伯防備隊(大分県)が担当した。昭和一七年一〇月のこの隊の陣中日誌が遺されているが、その付図にはこの水道一面に水中聴音機及び敷設機雷堰の記入が見られる。この時期に既に厳重な警備が施されていたものであろう。また陸上の要点には少数の将兵を駐在させていた。昭和一八年以降、防備隊は本県の由良岬に砲台・兵舎を構築したが、その細部は詳らかでない。これらの一部遺構は現存する。
〈松山海軍航空隊〉
昭和一八年初め、松山市郊外吉田浜に第19連合航空隊隷下の松山海軍航空隊が設置され、甲種飛行予科練習生(略称予科練)の養成に当たった。これは航空兵員の初期練習を担当するもので、終戦までに第13~第16期生約一万五千名を訓練して送り出している。昭和一九年には宇和島にも一部を分遣し、同地でも訓練を行った。
昭和二〇年六月、航空機機材の払底と本土防衛の必要から急きょ陸戦隊に改編され、「緑部隊」と呼んで城辺町から宿毛(高知県)にわたり配備されて終戦を迎えた。
〈松山を基地とした海軍戦闘機隊〉
松山海軍航空隊に隣接する吉田浜航空基地は、第1航空艦隊所属の海軍航空隊が基地として使用した。昭和一八年一○月には263空(豹部隊、司令・中佐玉井浅一、艦上戦闘機零戦)が、同年一一月には341空(獅部隊、司令・中佐小笠原章一、艦上戦闘機零戦)がそれぞれ開隊し戦闘訓練を行った。
昭和一九年一二月には343空(剣部隊、司令・大佐源田実、局地戦闘機紫電改)が開隊し、同隊の編成次いで猛訓練を開始した。昭和二〇年三月一九日、四国沖の空母群から発進し呉軍港攻撃に向かった艦載機数一〇〇機に対し、343空は一斉に迎撃に飛び立ち、松山周辺において激しい空中戦を演じてその数一〇機を撃墜する戦果をあげた。この後343空は基地を九州の鹿屋・大村に移して善戦を続けたが、物量の差の前にその戦力は次第に損耗していった。
〈特殊潜航艇訓練基地〉
太平洋戦争開戦へき頭、真珠湾攻撃に参加した特殊潜航艇の訓練基地として佐田岬半島瀬戸町三机港が用いられた時期があった。特殊潜航艇は昭和七年ころから秘かに研究開発が進められていたもので、試作艇を改造した二艇が昭和一五年四月及び六月に完成し、同年九月には正式兵器に採用された。秘匿上この艇は「甲標的」と呼ばれた。一方、これを塔載する母艦「千代田」(昭和一三年水上機母艦として竣工、基準排水量一万一、一九〇トン)も昭和一六年一月に第2甲運送艦としての改装工事を終えて艦隊に編入された。乗組員の訓練の中、座学及び机上演習は呉沖烏小島で行われ、五月以降三机基地沖の伊予灘において母艦からの投下訓練に進んだが、八月一八日の襲撃訓練においては、魚雷を目標艦「千代田」に命中させ、成功裡に三机での訓練を終了した。この後九月には訓練基地を真珠湾口によく似ている宿毛の中城湾に移し、防禦網切断などハワイ攻撃に取り組んだ応用訓練を開始した。連合艦隊の山本司令長官は、この艇による真珠湾奇襲攻撃について、当初は襲撃後の艇員の収容の見込みがないことから再度に渡り採用を却下したが、航続時間延長を研究するなど部隊側の熱意に動かされて遂に暗黙の承認を与えるに至った。
昭和四一年八月、三机海岸に真珠湾攻撃に参加した岩佐中佐以下九軍神の慰霊碑が建てられた。
(2)陸軍関係
〈第3航空教育隊〉
補充隊までも動員して次々と前線に送り出した松山市堀之内の兵舎には、その後歩兵部隊が設置されず、第3航空教育隊が移駐して隊員教育に当たった。この教育隊は、陸軍航空整備に関する兵員教育を行う機関で、最初は台湾嘉義において昭和一二年一二月創設された。その後一六年一月、熊本県菊池に移り、更に一九年二月、松山歩兵第22連隊跡兵舎に移駐した。教育隊(長・大佐宿利十三郎)の人員は一時七、〇〇〇人に達し、航空整備に関し機関・電気・自動車・武装などの教育訓練を行った。その後航空機機材の払底に伴い、重信川付近の秘匿飛行場の設定警備などに任じ、その一部は周桑郡丹原町にも派遣されていた模様である。昭和二〇年二月に新教育隊長(大佐西岡延次)が着任するが、同七月一八日、この教育隊は復帰(解散)している。本土決戦に備え本土防衛軍の編成が急務とされた時期なので、隊員は再びこれら地上作戦師団に転属する者が多かったと考えられる。
七月二六日夜の松山空襲によって堀之内の兵舎もその大半が炎上したが、この時堀之内には松山連隊区司令部とこの教育隊の残務整理の人員若干名が残っていたに過ぎなかった。
〈佐田岬砲台〉
西宇和軍佐田岬の突端の灯台付近には、陸軍の要塞重砲が配備されていた。これは大正八年に制定された「要塞整備要領」により、豊予要塞の一環として築造が決定したもので、同一〇年着工し、同一五年完成した。太平洋戦争が始まった後は、豊予要塞は西部軍に隷属し、司令部を対岸の大分県佐賀関町に置いた。
昭和二〇年二月、応急兵備(四国防衛軍の項参照)の実施とともに第16方面軍(司令部福岡県二日市、九州の防衛担当)の戦闘序列に編入され、対岸九州の諸砲台と呼応して豊予海峡の防衛に任じた。佐田岬砲台の備砲は四門で、初め15加砲、後に12榴砲に改められた(「三崎町誌」)。
|
図4-13 第40師団作戦地域図 |
図4-14 アキャプ付近見取図 |
図4-15 第二次アキャプ作戦 |
|
図4-16 ポートモレスビー海路攻略作戦経過 |
図4-17 第一次バタアン攻撃進路図 |
図4-18 昭和18年吉田浜航空基地 |

 えひめの記憶 キーワード検索
えひめの記憶 キーワード検索