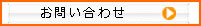第一展示室(学問)
| 名前 | 生年・没年 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 凝然 ギョウネン |
1240~1321 |
鎌倉時代中期の |
伊予国越智郡高橋郷( 現今治市)に生まれる。18 歳のころ東大寺の円照に師事。華厳、倶舎、律、三論、成実、法相、天台、真言、禅、浄土などの各宗に精通した学僧として知られる。「八宗綱要」「三国仏法伝通縁起」など広範囲にわたる著作を遺し、著書の数は120 余部1200 余巻といわれる。 |
| 中江 藤樹 ナカエ トウジュ |
1608~1648 |
我が国陽明学の |
近江国高島郡小川村(現滋賀県)生まれ。9歳の頃伊予国に来て、長じて大洲藩家臣となる。朱子学を学び、後、近江に帰り陽明学を究め「近江聖人」と呼ばれた。 |
| 江嶋 為信 エジマ タメノブ |
1635~1695 |
今治藩家老 |
日向国飫肥(現宮崎県)藩士の三男に生まれる。京都で伊藤玄亀に兵学を、江戸で荻生徂徠に古文辞学を学ぶ。仮名草子「身の鏡」「理非鑑」を著し、兵法書も著す。寛文8年今治藩に仕え、元禄4年、家老となる。今治藩家老として、太田流軍学による藩の兵式体制の改革など藩政へ貢献した。 |
| 尾藤 二洲 ビトウ ジシュウ |
1747~1813 | 儒学者 |
宇摩郡川之江村(現四国中央市川之江町)生まれ。大坂(現大阪府)に出て、苦学の末私塾を開き朱子学の普及に尽くす。幕命で就任した昌平黌教授を約20年間務め、寛政の三博士の一人といわれた。 |
| 近藤 篤山 コンドウ トクザン |
1766~1846 |
儒学者 |
宇摩郡小林村(現四国中央市土居町)生まれ。大坂(現大阪府)で尾藤二洲に朱子学を学ぶ。川之江に開塾後、小松藩に招かれ、子弟の教育にあたり「徳行天下第一」と称され「伊予聖人」といわれた。 |
| 青地 林宗 アオチ リンソウ |
1775~1833 |
蘭学者 |
松山城下(現松山市)で、松山藩医の家に生まれる。杉田玄白の門下生として蘭学を修め、幕府天文方の翻訳方となる。我が国初の物理学書『気海観瀾』を著し、物理学を紹介した。 |
| 高野 長英 タカノ チョウエイ |
1804~1850 |
蘭学者 |
陸奥国胆沢郡水沢(現岩手県)生まれ。『戊戌夢物語』で幕政を批判し投獄されたが、脱獄して宇和島を訪れ、藩士に蘭学を教え、兵書の翻訳や御荘砲台の設計などを行った。 |
| 二宮 敬作 ニノミヤ ケイサク |
1804~1862 |
蘭学者 |
宇和郡磯崎浦(現八幡浜市保内町)生まれ。長崎でシーボルトの門人となり、シーボルト事件で連座し帰郷。宇和島藩に仕えながら卯之町で開業医として活躍。シーボルトの娘イネを養育した。 |
| 矢野 玄道 ヤノ ハルミチ |
1823~1887 |
国学者 |
喜多郡阿蔵村(現大洲市)生まれ。幕末に、国学の振興や王政復古運動に従事し、明治維新後は、政府に国家構想をまとめた意見書を提出。後に、皇典講究所の文学部長となった。 |
| 村田 蔵六 ムラタ ゾウロク |
1825~1869 |
蘭学者 |
周防国吉敷郡鋳銭司村(現山口県)生まれ。宇和島藩主伊達宗城に招かれ、宇和島で7年間にわたり蘭学の指導・普及、軍艦・砲台の建造などに従事した。後に大村益次郎と改名。 |
| 楠本 イネ クスモト イネ |
1827~1903 |
日本人初の女医 |
肥前国長崎(現長崎県)生まれ。シーボルトの娘で、二宮敬作に卯之町で養育される。石井宗謙に産科を学び、東京で開業。明治6年、宮内省御用係を拝命し、若宮誕生に携わった。 |
| 三瀬 諸淵 ミセ モロブチ |
1839~1877 |
蘭学者 |
大洲城下の中町(現大洲市)生まれ。二宮敬作に蘭学を学び、再来日したシーボルトの最後の弟子となった。楠本イネの娘高子と結婚。大阪に医学校兼病院を開設し、後輩の育成にも当たった。 |
| 穂積 陳重 ホヅミ ノブシゲ |
1855~1926 |
民法学者 |
宇和島城下の中ノ町(現宇和島市)生まれ。帝国大学法科教授として東京大学法学部の基礎を確立した。我国最初の法学博士で、民法・戸籍法などを編纂し「明治民法生みの親」といわれた。 |
| 穂積 八束 ホヅミ ヤツカ |
1860~1912 |
憲法学者 |
宇和島城下の中ノ町(現宇和島市)生まれ。東京帝国大学教授。明治法学界の重鎮となり、貴族院議員に勅撰され、宮中顧問官も務める。 |
| 西園寺 源透 サイオンジ ゲントオ |
1864~1947 |
郷土史研究家 |
宇和郡川内村(現宇和島市)生まれ。愛媛の政財界で活躍後、景浦稚桃らと「伊予史談会」を設立。郷土資料の収集整理や古文書の研究を行い、郷土史研究の先駆となった。 |
| 佐伯 矩 サイキ タダス |
1876~1959 |
日本における |
新居郡氷見村(現西条市)生まれ。明治38年渡米しエール大学で生理化学を学び、大正3年、東京白金に私立栄養研究所を設立、栄養改善を各地で説いて回った。大正9年、国立栄養研究所が開設すると初代所長に就任、栄養の総合的研究で世界的権威となった。 |
| 真鍋 嘉一郎 マナベ カイチロウ |
1878~1941 |
医学者 |
新居郡大町村(現西条市)生まれ。物療内科という新分野を開拓後、東京帝国大学医学部の教授として、内科物理療法学の講座を開いた。夏目漱石ら著名人の主治医を務めた。 |
| 穂積 重遠 ホヅミ シゲトオ |
1883~1951 |
民法学者 |
東京府東京市深川(現東京都)生まれ。東京帝国大学教授。家族法の権威といわれ、法律の民衆化に努め、法文・判決文の口語化を提唱した。後に、最高裁判所判事も務めた。父は穂積陳重である。 |
| 大野 作太郎 オオノ サクタロウ |
1886~1968 |
教育者 |
北宇和郡下鍵山村(現鬼北町)生まれ。小学校勤務のかたわら南予の地質研究に取り組む。魚成村田穂(現西予市)でのアンモナイトの発見は、地質学上世界的な発見として注目を浴びた。 |
| 矢内原 忠雄 ヤナイハラ タダオ |
1893~1961 |
経済学者 |
越智郡富田村(現今治市)生まれ。戦前に東京帝国大学教授として戦争政策を批判し、軍部に弾圧され辞職に追い込まれた。戦後、復職し、昭和26年に東京大学の総長に就任した。 |
| 細川 一 ホソカワ ハジメ |
1901~1970 |
医師 |
西宇和郡三瓶村(現西予市)生まれ。新日本窒素肥料(現チッソ)水俣工場付属病院長時代、水俣病を発見し、原因究明に取り組んだ。昭和34年、工場廃液を混ぜた餌でネコを発症させ、原因を実証。同45年、肺がんで入院中、裁判の臨床尋問で社内研究の結果を証言し、被害者勝訴に導いた。 |