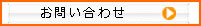第一展示室(教育)
| 名前 | 生年・没年 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 日下 伯巌 クサカ ハクガン |
1785~1866 |
儒学者 |
松山城下(現松山市)生まれ。藩命により昌平黌に入学し、朱子学を修得した。明教館の開設により教授として子弟教育に従事し、その門から、矢野玄道や大原観山らを輩出した。 |
| 大原 観山 オオハラ カンザン |
1818~1875 |
儒学者 |
松山城下(現松山市)生まれ。江戸の「昌平黌」に学び、帰藩して松山藩校「明教館」教授となり子弟教育に尽くした。維新の際、藩主松平定昭をよく補佐した。晩年は私塾で学生を教育。正岡子規の祖父にあたる。また三男の恒忠は、後に松山市長になった加藤拓川である。 |
| 新田 長次郎 ニッタ チョウジロウ |
1857~1936 | 学校創立者 |
温泉郡山西村(現松山市)生まれ。工業用ベルトを中心とする製革業や、関連事業を興す。また、大阪工業会の設立に尽力。現松山大学の創立にかかわるなど、教育の振興にも努めた。 |
| 山路 一遊 ヤマジ イチユウ |
1858~1932 | 教育者 |
松山城下( 現松山市) に生まれる。東京師範学校に学び、明治17 年、文部省に入省。29 歳で高知県師範学校の校長に就任し、以降、香川、兵庫、愛知、滋賀などの師範学校長を歴任した。大正2年、愛媛県師範学校長となり、教師となる生徒の人格形成に重きを置き、師範教育の改善発展に尽くした。 |
| 小川 尚義 オガワ ナオヨシ |
1869~1947 |
大学教授 |
松山城下(現松山市)に生まれる。台北帝国大学文政学部教授として、台湾語の研究に精進した。『日台大辞典』・『台日大辞典』等を著し、学士院恩賜賞を受けた。 |
| 安倍 能成 アベ ヨシシゲ |
1883~1966 |
哲学者 |
松山城下の小唐人町(現松山市)生まれ。カント哲学の第一人者。京城帝国大学教授・第一高等学校長を歴任。幣原内閣の文相として戦後の教育制度改革に尽力。後、学習院院長を務めた。 |
| 八木 繁一 ヤギ シゲイチ |
1893~1980 |
理科教育の貢献者 |
野間郡波方村(現今治市波方町)生まれ。多くの理科教員の養成に努める一方、県立博物館の設立に尽力した。また『愛媛の植物』等を著述し、植物分類学の基礎を築いた。 |
| 米田 吉盛 ヨネダ ヨシモリ |
1898~1987 |
学校創立者 |
喜多郡満穂村(現内子町)生まれ。騒然とした社会状況の安定には、自律した教養ある社会人を世の中に送り出すことが必要であるとの信念により、向学心のある学生に対し学習機会を提供できるよう、昭和3年横浜学院(翌年、横浜専門学校)を創立後、校長兼理事長となった。 |
| 冲永 荘兵衛 オキナガ ショウベエ |
1903~1981 |
学校創立者 |
喜多郡長浜町(現大洲市長浜町)生まれ。帝京商業学校の開設を手始めに、私立学校経営に取り組み、帝京大学を頂点とし、幼稚園に至るまでの一大総合学園を築いた。 |